- DENTSU
CREATIVE DIRECTOR/COPY WRITER
2021 61st ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS 審査委員講評
-
フィルム部門 審査委員長
 細川 美和子Miwako Hosokawa
細川 美和子Miwako Hosokawaフィルム部門 審査委員
 麻生 哲朗 Tetsuro Aso
麻生 哲朗 Tetsuro Aso- TUGBOAT
CMプランナー、クリエーティブディレクター
「新しい視点」とは何だったのだろうか。そんなものはあっただろうか。「なんだか腹の底から笑えないご時世」の中で、広告が時代を投影するというなら、つまらない時代はつまらない広告で仕方ないということだろうか。時代に寄り添うことも広告の当然の役割だが、時代を攪拌することもまた広告の大切な機能だと信じたい身としては、今年はどうしても感情の振り幅が小さい中での審査に感じてやや寂しくはあった。そこに新しさを見出そうとすると無理があるようにも思った。その上で、審査員たちが新しさのように拠り所にしていたものは「忘れかけていたもの」だったのではないかと思う。それが数多見つけられた結果だとしたら、激しい自省と共に復興の兆しはあると信じる。
 阿部 薫 Kaoru Abe
阿部 薫 Kaoru Abe- ソーダコミュニケーションズ
エグゼクティブプロデューサー
「新しい」ってなんだろう…何度も自問自答した。審査委員の一人としてフェアであったか、意思を持って審査できたか、もたくさん考えた。
今年はコロナ禍におけるあたらしい生活様式、東日本大震災から10年、S D G Sとの向きあいかた、などをとらえた広告が多かった。エモーショナルに寄りすぎず、独自性があり、良き文脈で表現されているものが2021年に賞を獲るべきC Mなのかなと思った。ドキュメントの強さや、逆に現状を上手なドラマ(フィクション)で紡げているものを評価した。結果、骨太なC M、セリフがきちんと耳に残ることや構造の素晴らしさを選ぶ傾向にあった。 上西 祐理 Yuri Uenishi
上西 祐理 Yuri Uenishi- アートディレクター、グラフィックデザイナー
歴史あるCM部門の審査に初参加させていただいた。
メディアが同一である分、様々な技術や手法や絶妙が際立ち、
広告制作者として以前に、いち視聴者として、
心を掴まれるものに多く出会った審査だった。
普段専門としているグラフィックとはまた違う時間軸をもった仕事たちに、
ユーモアの力強さや吸引力を強く再認識させられた。
また言葉の強さ、感情を突き動かす映像やメッセージにも、学びが多かった。
近年なんでも説明できることが求められ、
それは大切なことではあるけれど、
「説明はできないけどなんか好き」の良さも信じる身としては、
それが残っている部門と感じ、その点も嬉しかった。 太田 麻衣子 Maiko Ota
太田 麻衣子 Maiko Ota- 博報堂クリエイティブ・ヴォックス
クリエイティブディレクター
「いい広告はいい質問でもあるんだって。答えを見せてるのは嘘だって。答えなんて決められないんだって。これがいい答えだろうって決めて言っちゃダメなんだよ、いい広告は」って言ってる人がいます。私の師匠の言葉です。「当たり前を疑え」と同時に、この時代にこの世の中に、いい質問を出せているのか、と考えながら審査に参加していました。クラフトに大技ありも、洗練されたユーモアも、気の利いたセリフももちろん楽しめましたが、いい質問にまで到達できれば、それは制作者も誇りに思っていい広告だと思います。難しいなあ。でも今年たくさんありました、チャーミングないい質問。見ている人を心底笑わせたり、泣かせたり、考えさせたりしながら。
 太田 恵美 Megumi Ota
太田 恵美 Megumi Ota- 太田恵美事務所
コピーライター
過去の蓄積から予想するマーケティングなんかより遥かに、人の感受性は多様だ。だから「新しい」が生まれる。だのに広告主ばかりか広告の企画者までが、その当たり前に知らんぷりしてはいないか。というわけで審査委員長から出された審査のキーワードは「新しいチャレンジ」「新しい視点」だ。新しいってなんだろう。今を疑ってみる、安直に折り合いをつけない、もっともっと考える。そんな態度のことか。ただしプロなら、態度以上に結果を問われる。その新しさは人を自由にしたか、幸せな時間をつくり出せたか、だ。だから、審査では「今までにあった、なかった」を評価軸にはしないことにした。だいいち、人って、そんなカンタンに変わらないから。で、審査では、表現や手法というより、心と身に、驚きと快感の両方が宿ったものはどれかを語り合えたような気がする。そして、結論はご覧の通りだ。
 尾形 真理子 Mariko Ogata
尾形 真理子 Mariko Ogata- Tang
クリエイティブ・ディレクター、コピーライター
わたしたちが広告を作るとき「今までの当たり前を変えよう」と思っているわけではありません。商品と、サービスと、ブランドや企業と向き合い、試行錯誤(七転八倒?)し、最適解を探していく。そうやって生まれたアウトプットに、制作者の隠れた願い(もしくは野望?)があるのだと思います。閉塞的な空気に少しでも風を。思い込みに自由を。破顔のきっかけを。制作段階でその願いを手離す事情は数多くあれど、そうなるといとも簡単に「当たり前」になってしまう。「見る価値なし」とスキップされてしまう。コロナ禍で痛感したことは、自分の価値観の狭さと偏りでした。それでも「当たり前」を飛び越えて作られた数々のCMは、あたらしい扉を開いてくれる。広告の可能性を拡張してくれている。そういう仕事への敬意が、賞となる審査方針であったように思います。
 尾上 永晃 Noriaki Onoe
尾上 永晃 Noriaki Onoe- 電通
プランナー
とにかく勉強になりました。
僕なぞが何か語るのもなんなので、
先輩方による痺れた発言のお裾分けをさせていただきます。
「プランナーがディレクターに負けていないか。」
「コピーが持ち上げられすぎて不自由になってきている。」
「ほんとのリアルは汚くてみたくない。だから表現で化粧する。」
「作っている側のやってやろうって気持ちがでているか。」
「(単体で終わらず)読後感の長い設計も必要なのではないか。」
「思わずみちゃうとか、音がいいな、とかも大事。」
「仕組みが新しい表現を呼び寄せる。」
「この仕事によって、このジャンルがみんなが取り組みたいジャンルに変わった。」
ずっと耳が痛い審査会でした。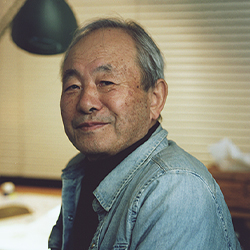 小田桐 昭 Akira Odagiri
小田桐 昭 Akira Odagiri- 小田桐昭事務所
クリエイティブディレクター・イラストレーター
コロナ禍の中のACCは、広告が「閉じられた暮し」の中で、人々にどんな価値をもたらしたのかを考えるいい機会でもあった。
大塚製薬の「カロリーメイト」と「ポカリスエット」は、何れもコロナ禍の中での若い人たちの鬱積したものを「カロリーメイト」は寄り添うように、「ポカリスエット」は撥ね返すように表現している。ブランディングというマーケティング上の目的と同時に、人々に勇気や希望や楽しさを与えたいという文化的な役割も同時に果している。広告だがらこそ、高い制作費を、もっとたくさんの人たちに見て貰うためのメディア費も払うことが出来る。サントリーの「365歩のマーチ」も「BOSS」というスポンサーがついていることに意義がある。「ポカリスエット」の実験的映像も、こんな時だからこそ「見たことのないものを見せたい」という制作者たちの高ぶりと、彼らの「冒険」を支えるクライアントの心意気といったものが伝わってくる。「普通を大切に」と、あらゆるものが小ぶりになってゆく制作物、「ポカリスエット」について、もう少しディスカッションがあってもよかったのに、と思う。 篠原 誠 Makoto Shinohara
篠原 誠 Makoto Shinohara- 篠原誠事務所
クリエーティブ・ディレクター
私は、あまり審査というものをしたことがない。ここ数年で何回する機会をいただいたが、審査はいつも、難しい。自分がいいと思ったものが、選ばれないことの方が、多い。でも、だからこそ、一生懸命にいつも審査する。1次審査から、何度もちゃんと見て、繰り返し審査する。見る順番に左右されないように、繰り返し見直す。今回の審査基準と、自分の審査基準を1対1で入れ込んで、審査した。企画のはじまりから、納品の最後まで、手を抜かず磨き込んだ広告、そして、その広告が効いた感触があるものに票を入れた。応援演説もした。人が作った広告の。審査後に感じたことは「まだまだ自分がんばれ」だった。自分自身を審査したような気がした。
 東畑 幸多 Kota Tohata
東畑 幸多 Kota Tohata- 電通
エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター、CMプランナー
コロナ禍になって、エッセンシャルワーカーという言葉が生まれた。
同時に、ブルシットジョブという言葉も生まれた。日本語に訳すと「クソどうでもいい仕事」。その代表として、広告マーケティングの仕事が名指しされていた。
僕たちの仕事は、一瞬でも気を抜くと、ブルシッドジョブ側に行ってしまう。カロリーメイトをはじめ、ACCの受賞作を改めて見ると、作り手の態度次第で、エッセンシャルは言い過ぎかもしれないが、「あってよかった仕事」になれることを教えてくれる。クソどうでもいいに抗う人が一人でも増えてほしい。そして、自分もその一人でありたい。審査会が終わって、強くそう想った。 箱田 優子 Yuko Hakota
箱田 優子 Yuko Hakota- CluB_A
ディレクター
今年はコロナ禍である事にプラスして、様々な価値観が変動を見せる年だった。そんな中、広告が視聴者にどう語りかけるか、どう観せていくか、ナイーブな状況を加味しながらの表現に息苦しさを感じたのが正直なところだ。受賞したものは皆クリエイティブの力と共にそこを打破する「気持ち」のあるものが選ばれたと感じた。
……なんて真面目な言葉で始めてみましたが、そこはきっと他の審査委員の方が素敵な言葉で書かれてる事でしょう!困難な状況下だからこそユーモアが必要だと感じましたし、何言っても叩かれがちな世の中で、萎縮せず、えいやあやったれ!とバット振り切ってる物の清々しさったらなかったです。観客席からありがとう言いました!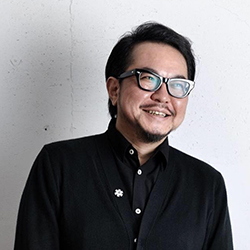 原野 守弘 Morihiro Harano
原野 守弘 Morihiro Harano- もり
クリエイティブディレクター
審査結果に違和感を感じる人も多いと思う。ACCは身内で賞を回しあっているという批判が絶えない広告賞だ。今年も結果的にそうなっている感は否めない。
カンヌなどでは、作品について議論をする場合は、利害関係者は部屋の外に出される(Zoomでも同じ)。ACCはそれをやらないため、つくった本人がいる前での議論になる。忖度を感じる発言も多かった(議事録参照)。
また、銅賞以上を決めてから、いきなり金賞を決めるという審査プロセスも非合理的だ。多くの国際広告賞では、銅→銀→金と下から決めていく。
はじめての参加だったが、いろいろ課題が多い。審査委員から利害関係者を徹底的に排除すること、合理的な審査プロセスとルールを明文化すること、この2点がまず必要と感じた。 林 響太朗 Kyotaro Hayashi
林 響太朗 Kyotaro Hayashi- DRAWING AND MANUAL
Director
はじめて審査委員としての視点で多くの広告を見た。そして多くの価値観で審査した。全ての作品に各々に考えがあって、それを審査する考えがあって全ての意見が自分の栄養分になっていくのをビシビシと感じる時間だった。こんなに長くて、沢山栄養のあるオンライン審査に参加できて光栄だったのと同時に、1つ強く芽生えたこともあった。
美しいものを美しいと言える人でありたいと強く思った。この国にこの映像があって良かったと思えるものを作り出していきたい。そんな風に思う思いあえる仲間とこれからも良いものを作っていきたいなと思った。 福里 真一 Shinichi Fukusato
福里 真一 Shinichi Fukusato- ワンスカイ
クリエイティブディレクター、CMプランナー、コピーライター
審査がはじまる前に危惧していたのは、今回審査委員になられた小田桐昭さんが、いまのCMたちを見て、「全部よくない!」とおっしゃり、史上初の、「ブロンズ以上全賞該当作なし」という事態になること。それもまたよし、と思って審査に臨みましたが、実際には小田桐さんは、Aカテグランプリのカロリーメイトや、Bカテゴールドのそごう西武、ほかにも木村拓哉さん出演の「マック、みっけ」のシリーズのことなどもカジュアルにほめていて、別に私がいまのCM代表というわけでもありませんが、とりあえずほっとしました。むしろ、もっと厳しい審査委員はほかに…どなたとは申しませんが。受賞作全体としては、まあとにかく、福部明浩さんの活躍がすさまじく、グランプリのカロリーメイトはもちろん、日清「どんぎつね」、キリンホームタップ、クラシエHIMAWARIなどなど。こういう方には個人賞をあげてもいいのではと思うのですが…プロ野球みたいに「今年度MVP」みたいな賞を、今後つくってもいいのかもしれませんね。細川審査委員長の、ゆっくりした中にもキリリとしたものがひそむ審査委員長ぶりも、印象的でした。おつかれさまでした。
 福部 明浩 Akihiro Fukube
福部 明浩 Akihiro Fukube- catch
クリエイティブディレクター、コピーライター
実はもう審査からずいぶん経っていて、
なんなら年を跨いでこの文章を書いているので
(事務局の方々、スイマセン。。。)
審査過程も、審査結果も完全に自分の中では
「過去」になってしまっているのですが、
だからこそ冷静に振り返れる部分も多々あります。
中でも一番心に残っているのは、結局なんで
ポカリってゴールド以上じゃなかったんだっけ?です。
僕は同じ大塚製薬でカロリーメイトを担当していて
ある意味一番のライバルでもあるので、
中島セナちゃんが廊下を走り抜けた映像を見た瞬間、
「あ、抜かれた・・!」という感触が確かにありました。
それはこの年、同じ速度で走っていたライバルだからこそ
見える景色だったと思います。そして多分ですが、
世の中の体感も、そういう感じだった気がします。
「いま鮮烈なCMが、目の前を走り抜けた!」
審査から本当にずいぶん時間が経ったし、細かい議論の内容は
忘れてしまったけれど、僕はこの年のことを思い出す時、
絶対その1ページに、あの疾走する中島セナが入っていると思う。
広告が機能するスパンは、僕らが想像する以上に
実は長いものなんじゃないかと最近思ったりしています。 古川 雅之 Masayuki Furukawa
古川 雅之 Masayuki Furukawa- 電通関西支社
グループ・クリエーティブ・ディレクター、CMプランナー、コピーライター
審査会に出て「勉強になりました」ばかり言っていても仕方ないのだけれど、とても勉強になった。褒めること、票を投じることよりも問題は、投じないものをどう決めるかだ。たとえば10本選ぶとして、最後に投じる10本目と、投じないことになる11本目の差を明確に説明できるか。なぜそこに線を引いたのか。何の差なのか、アイデアかクラフトか文脈か、構造や話法の新しさか好き嫌いか。ベテラン審査委員たちのなぜこれがいいのかの深い洞察、そして投じなかったCMへの明快な理由に自身の判断はぐらんぐらんと揺れた。アタマの中で意見を反芻し、結局最後は耳を塞いで、制作者として視聴者として自分の心が動いたものを選んだ。カロリーメイトの底力。
 真子 千絵美 Chiemi Manako
真子 千絵美 Chiemi Manako- 電通
CMプランナー、コピーライター
応募作品を見ているときから、審査委員の方々と議論をしているときまで。
沢山の「新しい視点」に出会えた、すごく幸せな時間でした。
一目で新しいと思う表現や仕組みだけではなく、
メッセージや姿勢など、今までの自分に新しい気づきをくれるもの。
そんな映像が、そんな映像を作っている人たちが、改めて好きだなと感じました。
個人的には、過去61年の中でもTHE FIRST TAKEの受賞は新鮮で、
今年多くの人に愛されたコンテンツが映像の仕事であることがとても嬉しく、
フィルム部門の歴史を更新したのではと思います。
一人若手で実力も経験も乏しい中で、
丁寧に耳を傾けてくださった審査委員のみなさま、本当にありがとうございました。 - TUGBOAT
-
ラジオ&オーディオ広告部門 審査委員長
 井村 光明 Mitsuaki Imura
井村 光明 Mitsuaki Imura- 博報堂
第三クリエイティブ局 クリエイティブディレクター
注目すべきは審査委員の方々から「面白い」ではなく「心地いい」という言葉が幾度も出る審査会だったことです。文字原稿で見たとしたらとても普通なはずなのに、なぜか60秒間自然と聞いてしまったゴールドの「アイベックスエアラインズ」。そして、「名言を吐くよ」と始まるものの音楽だけで30秒引っ張るグランプリ作「虫コナーズ」。前者は声のトーンやスピード、後者は隙間。テイストが全く違う2作品ですが両者から感じられたのは、身体にスッと入るよう情報濃度が調節された、生理食塩水的とも言える心地よさでした。
毎日スマホで動画を見る時代、SNSから繰り出されるテキストに知らず知らず圧を感じてはいないでしょうか。情報ストレスの中で広告効果を生み出すには、耳から入る情報量くらいがちょうど良いのではないか。むしろ音声だけの方が効率的に伝わる時代になっているのかもしれない。近年ラジオや音声配信サービスのリスナーが増えている理由もここにあるのではないでしょうか。
ACC7部門のグランプリ作を並べて視聴してみてください。きっとラジオ&オーディオ広告部門でホッとするはずです。それこそがこれからの音声コミュニケーションの可能性を示唆しているように思うのです。
ちなみに本年度募集範囲を拡大したBカテゴリーは作品の広がりを感じられるものとなりました。募集要項を更に精査することでBカテ初のグランプリが登場するのではないか、そんな手応えもありました。ご応募いただいたみなさん、誠にありがとうございました。ラジオ&オーディオ広告部門 審査委員
 荒木 美和 Miwa Araki
荒木 美和 Miwa Araki- NHK 国際局国際企画部
展開プロモーション担当
異業種からの参加で別の視点を提供できるのではと、今回参加させて頂きましたが、数多くの素晴らしいクリエイティブとの出会いと審査委員同士の意見交換を通じて、大変貴重な学びの機会を与えて頂きました。
現在、NHK WORLD-JAPANの番組のプロモーションを担当し、文化的背景や生活様式の違う海外の視聴者にどうすれば番組を届けられるか暗中模索の日々です。今回の審査会に参加してクリエイティブに求められる根っこは同じだなと感じる部分もありました。
今回はリモート審査会でしたので、他の審査委員の方と阿吽の呼吸で議論を積み上げていく…という訳にはいきませんでしたが、その分本音が垣間見える審査会だったと感じています。 井上 佳央里 Kaori Inoue
井上 佳央里 Kaori Inoue- Radiotalk
代表取締役
映画と違った楽しみが小説にあるように、音声だからこそ駆り立てられる情緒が個人的に好みです。ただこれはマニアの楽しみ方で、ラジオを「聴いたことがない」人に最初から「じっくり聴けば面白い」音声を聴いてもらうのはなかなか難しいと、音声プラットフォームを立ち上げて実感していました。
インターネットのエンタメにおいて、NetflixプレビューやInstagramリール、YouTubeショート動画など短尺から関心を惹いて本編へ誘導することがトレンドです。ラジオCMは、非リスナーの方をラジオの世界に惹き込む短尺音声になると思います。ながら聴きの中で、目が覚めるように「耳が覚める」体験のある作品に投票しました。 澤本 嘉光 Yoshimitsu Sawamoto
澤本 嘉光 Yoshimitsu Sawamoto- 電通
シニア・プライム・エグゼクティブ・プロフェッショナル、エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター
コロナ禍でのリモート審査も2年目だったが、やはり直接顔を合わせるのと審査の雰囲気が随分と違う。いい意味で言えば、その場の雰囲気、とか、流れ、というものがあまり影響せずに付けた得点に従って淡々と決まっていく印象、つまり、聞いたままの印象が順位に結びつく。ただ、議論してそのCMのいい部分や未来へつながる部分を人の顔を見ながら語ることもさらに大きな意味で結果以上にラジオCMのためになることなので、それがどうしても減ってしまうのは残念だったが、審査委員長の井村さんはそこを最小限のダメージにとどめようと努力されていた。
 嶋 浩一郎 Koichiro Shima
嶋 浩一郎 Koichiro Shima- 博報堂/執行役員
- 博報堂ケトル/クリエイティブディレクター、編集者
大日本除虫菊のラジオCMにおける状況設定は想像の域を超えている。「金鳥虫コナーズで名言をはくよ」って突然言われても、「え、なんでそんなことする必要あるの?」って思うのが普通。だが、ある意味ありえない状況に聴き手を連れ去れるというのがラジオの力。聴覚だけのメディアは聴き手の想像力を掻き立てる。音声コンテンツが再注目される今、聴き手のクリエイティビティを刺激する技術について議論できてよかった。
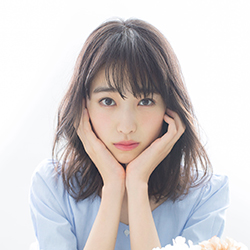 髙橋 ひかる Hikaru Takahashi
髙橋 ひかる Hikaru Takahashi- オスカープロモーション
女優
音の可能性、魅せ方を教えていただきました
私は普段、作っていただいた骨組みに添って膨らませたイメージを体現するお仕事をしています
「音のみ」という限られた表現方法でも、聞き手に色んな解釈を持たせてくれる面白い作品がたくさんありました
審査委員の皆さんそれぞれの目線で作品について
話し合うなか「構成が上手い」「なぜか惹かれる」など色んな意見が飛び交う中
リスナーとしての私の意見は「なぜか惹かれる」これにすごく共感するんです
「ついこのCM聞き入っちゃうなぁ」とか「口ずさみたくなっちゃう!」とか
無条件に魅力を感じるものってありますよね
今回の審査でその魅力の裏に隠された、作り手の努力を知り、よりリスペクトが深まりました
音の世界って、ラジオCMってやっぱり面白い!!! 橋本 吉史 Yoshifumi Hashimoto
橋本 吉史 Yoshifumi Hashimoto- TBSラジオ
プロデューサー
前回はコロナ禍に直面した各企業が、その戸惑いも含めてエモーショナルな非日常のように表現されていたが、今回はそれが日常として咀嚼されラジオCMになってきていると感じた。
グランプリの大日本除虫菊「虫コナーズで名言を」シリーズは、発想の独創性、音の作り込みのコストなど王者・金鳥のさらなる高みを感じさせる凄まじいクリエイティブだったが、何より、「深く考えさせず楽しい音声コンテンツ」であることがまさに2021年のムードにマッチしていた。「かっぱクリエイト」のミュージカル的なCMは最後まで聴き応えあるまさに「かっぱ寿司イン・ザ・ハイツ」といった風情でこれもまた楽しさが全面に出る作品。 畠山 侑子 Yuko Hatakeyama
畠山 侑子 Yuko Hatakeyama- 大広WEDO
コピーライター、プランナー
ある意味。審査委員だけでラジオCMを企画して、演じて、流して、ニュースに乗せられる今年のメンツ。知恵熱が出ました。バラバラの人種が唯一共通でなんども口にしていたのが「ズンバラバッバ」。全員に流通する企画だとグランプリに推しました。面白いのは、今年のACCを総なめしたThe first Takeが、この部門にはエントリーすらされていなかったこと。音声がキテる時代と言いながら、昨年から80も減ったエントリー数。音声CMにかけられない予算。
そんな今こそ、まわりと違う土俵で企画してる人は目立つ。シナリオだけで勝負せず、今までない収録の仕組みをつくったり、聴覚×別の感覚をかけ算したり。パイが少ないって、チャンスがあるってこと。 福居 亜耶 Aya Fukui
福居 亜耶 Aya Fukui- 電通関西支社
CMプランナー、コピーライター
年々、減っているもの。年賀状の数。日本の人口。世界の森林。そして、J-POPのイントロ。平均秒数が年々減っているそうです。経年変化グラフを見ると、きれいに短くなっていました。
グランプリの「虫コナーズで名言を」は、聞けば聞くほど、どんどん癖になる。求心力があるというか、もしかしたら、これ、日本人が忘れかけている/若者は知らないイントロの魔力というものじゃないか…!期待、緊張、からの脱力…。聴取を重ねるリスナーと同じ気持ちで、どんどん魅了されました。ACCはコピーの賞ではなく、広告の力に対する賞なんだなと改めて思い知った審査会でした。 古川 雅之 Masayuki Furukawa
古川 雅之 Masayuki Furukawa- 電通関西支社
グループ・クリエーティブ・ディレクター、CMプランナー、コピーライター
井村審査委員長は声がいい。その軽妙な語り口はあっと言う間に、気軽に意見を言える場を作り出した。井村さんにそそのかされ審査委員それぞれがニコニコと「思ったままのこと」を言う。おどろいたのは、みんな全然意見がちがうということだ。そもそもラジオCMとの関係のあり方も各々である。ラジオCMに求めているものもちがうし、意見をよくよく聞くと、なにを面白いと感じるかそのポイントもまったくバラバラ。同じ評価をしてるものでも、実は評価している箇所がちがったり。つまり、これはもう、ラジオCMを作る時には自分がいいと思ったものを作ればいいということなのだ。ラジオはそもそもパーソナル。誰かひとりにぐっさりと刺さればいい。
 森田 一成 Kazunari Morita
森田 一成 Kazunari Morita- ビッグフェイス
コピーライター、ディレクター
初めての審査会。リモート審査の難しさは感じながらも、楽しく審査させていただきました。
ファイナリストにも良いものが多く、ブロンズとファイナリストの差はそんなにないように感じました。
シルバー以上の上位作品を自分なりに分析すると、テクニックや古典的な枠組みに頼ってないものが今年は多かったように思えます。
あと、音や声に込められた想いや気合いがパッケージングされたものが上位に来た印象もあります。
応募作にはまだまだ旧来の枠組みのCMも多いので、新しいものを作れば評価される状況です。
ラジオCMで目立ってやろうと思ってる若い制作者にとっては、今はチャンスだとも感じた審査でした。 横山 雄二 Yuji Yokoyama
横山 雄二 Yuji Yokoyama- 中国放送アナウンサー
映画監督・俳優・作家
バカバカしければバカバカしいほど、熱のこもったプレゼンの様子が目に浮かぶ。くだらなければくだらないほど、クライアントの願いにも似た決断が想像出来る。子どもの頃、好きな番組のCMをカットしようとラジカセの一時停止ボタンに指を掛けていた自分を思い出した。あのときの自分に教えてやりたい。「CMって侮れないぞ」と。普遍的な作品。奇をてらった作品。ミュージカル調。様々な作品を聞くうちに腑に落ちた。「コロナ禍だから元気を」「こんな時期だから優しさを」CMは時代の写し鏡。テクニックではなく「ぬくもり」を演出した作品が集った。CMには聞く人の心に入り込むパワーがある。審査会終了後、なぜか「さぁ、オレもやるぞ」と意気込んだ。
- 博報堂
-
マーケティング・エフェクティブネス部門
審査委員長 鈴木 あき子 Akiko Suzuki
鈴木 あき子 Akiko Suzuki- サントリースピリッツ
執行役員 RTD・LS事業部長
最終審査会の議論の中で毎年必ず出る「グランプリは一つじゃなければいけないのか」との問題提起(というより、嘆き)。それほど、上位に残ったプロジェクトにはそれぞれ違った魅力がある上、業界も狙いも規模感も異なっているので、同列に論じることが難しいのです。それでも、最後には苦しみながら「今年の一等賞」を選びますが、そこにはその時々の審査委員の価値観、時代背景が反映されるものだと思います。私自身は常に、世のマーケッターを刺激し勇気づける賞であることを念頭に置いています。
今年の最終審査会では私自身も悩みに悩みましたが、各業界から集まった経験豊富で人間力に溢れる素晴らしい審査委員の皆様との熱い議論の末、「THE FIRST TAKE」をグランプリに選出しました。終わってみれば、やはり今年は「THE FIRST TAKE」しかなかった!という印象です。
「THE FIRST TAKE」は、CDセールスが低迷する音楽業界において、アーティストや楽曲が売れる仕組みそのものを変えました。私たち生活者に音楽との新しい出会い方を提供し、アーティストのありのままを見せることによって音楽の価値を鮮やかに再定義しました。音楽業界を後で振り返ったときに、「THE FIRST TAKE前」と「THE FIRST TAKE後」で歴史が分けられるくらいの発明だったのではないか。マーケッターなら誰しも、業界を一変させるゲームチェンジャーになってみたいはず。私自身、そんな嫉妬にも似た憧れを感じました。拍手喝采です。マーケティング・エフェクティブネス部門
審査委員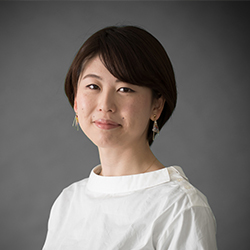 大澤 あつみ Atsumi Osawa
大澤 あつみ Atsumi Osawa- トヨタ・コニック・プロ
ブランディング部 主任
今年も審査会での議論を通じてたくさんの新しいアイデアやクリエイティビティに触れ刺激をいただきました。
生活者の声に真摯に向き合い、課題に対して丁寧にそして地道に対策を実施し続けることが、当然のことながら大切ですね。
わかっていてもそれを実践することが難しかったりする中、各社様のお取組みは大変すばらしかったです。
またこの部門ならではの公開プレゼンは、エントリーシートだけではわからなかった想いの部分を知り、印象が大きく変わることもあり、「伝える」ことの大切さも再認識しました。 太田 郁子 Ikuko Ota
太田 郁子 Ikuko Ota- 博報堂ケトル
代表取締役社長 共同CEO エグゼクティブ クリエイティブディレクター
受賞者の皆さん、本当におめでとうございます。今年は、ロングターム・ショートタームという視点が追加されたことにより、去年以上に審査しがいのあるエントリーがたくさんありました。時間をかけて地道に成果を残すことも、市場の変化に応じて瞬発力を発揮して成果を残すことも、マーケティングにはどちらも大事ですね(しみじみ)。そして、今年のキーワードは「仕組み」。マーケティング成果を残すために、どんな骨太な仕組みをつくったのか。単なるマーケティングアイディアではなく「仕組み」があると、一緒に戦ってくれる仲間を増やせたり、中長期的な競争優位が作れるってことなんだなと、とても勉強になりました。あらためて、素晴らしいプレゼンをありがとうございました。
 奥野 圭亮 Keisuke Okuno
奥野 圭亮 Keisuke Okuno- 電通
クリエーティブ・ディレクター
コロナ禍の1年。そんな危機的な状況でも、人は新しいアイデアを生みだし、世の中を明るくし前向きな気持ちにさせる生き物なのだと嬉しくなった審査会でした。例えば「THE FIRST TAKE」。ほぼ1年中、外出規制をされた今年、一体どれだけの人をワクワクさせたのだろう。そして、音楽の新しい経済圏を生み出し、ヒットの流通経路を一新した。その広告の枠を超えた経済活動に皆の票が自然と集まった。結局、マーケティングの基本は「人の心を動かす」ことなのだ。「驚き」「感動」「共感」が起点となり、大きな樹へと育てていく活動だ。今年、最終プレゼンに残ったどのチームも、大きな困難を乗り越えながら、人の心を大きく動かすアイデアを展開していたことがとても印象的でした。
 佐々木 亜悠 Ayu Sasaki
佐々木 亜悠 Ayu Sasaki- 電通
クリエーティブ・ディレクター
今年のME部門では、はじめて「ロングターム」でのマーケティングを意識した評価が加わりました。それもあってか、マーケティングそのものが本質から変わってきていることを改めて実感させられた時間でした。 手法の新しさや結果の残し方ももちろんマーケティングの革新なのですが、特にグランプリ受賞の「THE FIRST TAKE」やゴールド受賞の「絶メシ」のように、ひとつのアイデアが持続的・多面的に自走しながらいろいろな人々にとって利益を生み出す「装置」となっていった作品には、これからの時代のマーケティングのヒントがたくさんあったように思いました。受賞されたみなさま、本当におめでとうございます。
 白井 明子 Akiko Shirai
白井 明子 Akiko Shirai- ローソン
マーケティング戦略本部 部長
ME部門の特徴は最終公開プレゼンがあることかと思います。
紙ではわからなかったけれど、企画者のプレゼンを聞くことで、印象が変わる作品が多数あります。良くなる場合と悪くなる場合ありますが・・
マーケティング戦略成功者のプレゼンは、大変刺激なるので今後も続けていただきたいです。 高田 伸敏 Nobutoshi Takada
高田 伸敏 Nobutoshi Takada- 東急エージェンシー
クリエイティブ局局長 エグゼクティブクリエイティブディレクター
圧倒的。時代を切り取るとは、こういう事を言うのだろうか。アイデア、アートディレクション、フォーマット、すべてがシンプルで美しい。デバイスの向こう側の出来事なのに、そばで観ているかのように心臓がドキドキする。ファーストテイクという、一瞬の、ライブ感が伝わってくる。
コロナ禍の閉塞感の中、そのアイデアは瞬く間に人々を夢中にした。マーケティングは、時代と社会に寄り添っていくものだと思う。アイデアのあるもの、課題を鮮やかに解決するもの、持続性のあるもの、人々を楽しませるもの。生活者の心の中にある「音楽をもっと楽しみたい」という欲求にストレートに応えたこの素晴らしい企画に、グランプリをあげられたことが素直に嬉しい。 辻 毅 Takeshi Tsuji
辻 毅 Takeshi Tsuji- ADKクリエイティブ・ワン
クリエイティブ・ディレクター、コピーライター
油断すると火傷する!?審査会では本質を問う熱い議論が何度も交わされました。「THE FIRST TAKE」のグランプリ受賞は「エフェクティブネス」の意味をアップデートする大きな転機になるのでないかと思います。数字の結果以上に、アーティストの新たな価値を創造し、コロナ感染症拡大の影響で業績が落ち込んでいた音楽業界全体を元気にした功績は賞賛に値すると思います。うまい売り方を考えた企業やブランドが収益を独り占めする。そんな時代は終わりを迎えようとしているのかもしれません。企業やブランドの垣根を超えてみんながハッピーになれる仕組みを考える共創型マーケティングはこれからの主流になる。そんな予感がしました。今年も学びが多かった!
 西田 裕美 Hiromi Nishida
西田 裕美 Hiromi Nishida- カゴメ
マーケティング本部 飲料企画部長
今年の審査は、コロナ下で苦しい各業界で、従来のフレームや垣根を越えて新しい仕組みを生み出した「面のマーケティング」事例が多くみられました。グランプリを受賞した「THE FIRST TAKE」はコロナによる厳しい環境の下、音楽の究極の価値をボーダレスに伝える仕組みを構築し、成果を生み出しました。進化の背景には、課題に直面しても、チームの想いを一つにし、より良い未来に向けて知恵と努力を最大化し、細部に及ぶまで戦略を組み立て実行し、活動を進化させる、というマーケティングの基本プロセスがあり、基本に立ち戻る大切さを改めて教えて頂きました。受賞された皆様、本当におめでとうございます!
 平井 秀治 Shuji Hirai
平井 秀治 Shuji Hirai- ロッテ
マーケティング本部 中央研究所 執行役員
マーケティングとは?私は『効率的、効果的に物(有形、無形)を顧客に届ける仕組みをつくること』だと思っています。そのために重要なことはブランドを想起しやすい状態にし、そのブランドを手に取りやすい状態にすること。いつも頭の中にあるそのことと、どのような結果を導いたのかを評価基準として、初めてのACC ME部門の審査に臨みました。各作品、全てが高いレベルでその基準に達し、且つ大きな成果に繋げていて、審査が非常に難航し、何度も審査委員の皆さんと議論を重ねました。最後はやはりその中でも優れた仕組みであること、オリジナル性と新規性の面から順位が決まったと思います。非常に学びの多い、素晴らしい体験でした。
 松井 美樹 Miki Matsui
松井 美樹 Miki Matsui- 博報堂
執行役員
2021年マーケティングエフェクティブネスで印象的だったこと。それは、「渦」を巧みに生み出していくマーケティングだった。生活者の応援を取り込み、それを渦にして拡大させていくアプローチ。グランプリを争った、The First Takeと#ワークマン女子はまさにその典型だ。The First Takeは、視聴者とアーティストが共同して音楽ライブのドキドキを再発見していく、まさに共創プラットフォームだった。また、#ワークマン女子は、SNSで自然発生した言葉を出発点に生まれたハッシュタグ店舗が、また新たな支持者を生み出していくという、渦、連鎖反応を起こすマーケティングだった。両者に共通するのは、コロナ禍の生活者それぞれの中で、「積極的に生きよう、楽しもう」と思う気持ちに火を付けたことだったのではないか。パーパスを持った、生活者の渦を味方につけるマーケティングこそが2021年の特徴だった。ひとつの自治体のローカル活性化施策「絶メシ」が、生活者の支持の渦の中で、東京都心のリアル食堂へと発展していくマーケティングのあり方も、「パーパスを孕んだ渦マーケティング」として説明できるだろう。
 簑部 敏彦 Toshihiko Minobe
簑部 敏彦 Toshihiko Minobe- 花王
作成センター コミュニケーション作成部 コミュニケーション作成部長
マーケティングとはなにか、エフェクティブやリザルトをどう考えるか、クリエーティビティは?さらに今年はショートタームとロングタームのサブカテゴリーも加わって、ME部門は視点が複層的です。審査委員のバックグラウンドも様々で、縦横無尽に駆け巡る議論は刺激的で学ぶことばかり。多くの意見が飛び交うなか、マーケティングは仕組みをつくるものという軸でグランプリに輝いたThe First Takeは、「幸せの仕組み」を生んだのだと思います。コロナ禍で鬱屈とした空気も漂う時代に、一筋の光を届けたThe First Take。これからの展開も楽しみです。グランプリはじめ、受賞されたみなさま、おめでとうございます。
 宮園 香代子 Kayoko Miyazono
宮園 香代子 Kayoko Miyazono- ソフトバンク
東日本エリア営業本部 本部長
今年の審査会では、コロナがある日常が当たり前になってきた現状を受け入れて、マーケティングやコミュニケーションの工夫の仕方がまた一つ進化してきている印象を持ちました。複雑な世の中にもっと伝わりやすく。群で見せる、軸を変える、デザインを磨く…。既存のプロダクトやサーピスであっても、1つアイデアが掛け合わさることでより強くなり、世の中や気持ちが動き、エフェクティブネスを生む。それが多くの受賞企業で実証されていて勇気をもらいました。
受賞された各社のみなさま、本当におめでとうございます。 - サントリースピリッツ
-
ブランデッド・コミュニケーション部門
審査委員長 橋田 和明 Kazuaki Hashida
橋田 和明 Kazuaki Hashida- HASHI
クリエイティブディレクター
ブランドや社会の課題に向き合っている真摯な広告は、どんな形であってもいい。そんな思いのこの部門は、今年はDカテゴリー:ソーシャル・インフルーエンスを新設し、昨年を超える364の様々なやり方のコミュニケーションが応募されました。
Aカテゴリーでは、ビジョンステートメントを体感できるようにしたWEBサイト「POLA2029年ビジョン」が、クラフト力の高さに加えて、この時代に改めてWEBサイトの可能性を業界に指し示してくれたと思います。
Bカテゴリーでは、大王製紙のアテントがグランプリに。「オムツをパンツに。」「#常識をはきかえよう」といった強いコピーを軸に、販促だけではなく、カテゴリーの名前自体を変えてしまうような歴史的プロモーションだと評されました。
Cカテゴリーは、素晴らしいチャレンジが集まったのですが、グランプリはなしとなりました。ただ、そのチャレンジが種になり、大きく世の中を変えていくことができる可能性を秘めていました。
Dカテゴリーでは、成功させることが難しいYouTubeチャンネルを舞台に、大きな反響を読んでいる「THE FIRST TAKE」。アイディアであり、コピーであり、アートディレクションの力によって、様々なアーティスト、つまりインフルエンサーが自ら出演したくなるという仕組みをつくりあげ、ソーシャル・インフルーエンスのお手本となっていると思います。
4つの多様性豊かなカテゴリーがあるこの部門では、様々な得意分野をもった審査委員たちがあつまり、多様な目で審査されています。その中で受賞した仕事が指し示してくれているのは、新しいやり方を模索する態度だと思います。得意技を磨くのはもちろんのこと、得意技からハミ出す勇気を持って仕事に向き合えば、また新しい地平が見えてくるのではないでしょうか。ブランデッド・コミュニケーション部門
審査委員 飯田 訓子 Satoko Iida
飯田 訓子 Satoko Iida- Wunderman Thompson Tokyo
Associate Creative Director
多様性に富んだ、心を動かされるたくさんの仕事にふれることが出来ました。
そんな中でも際立って目をひくものは、“ブランドの存在のあり方”まで考え抜かれたクリエイティブでした。 “ブランドの存在のあり方”は言い換えれば、ブランドが私たちの生活環境の中にどうやって息づいていくかを考えること。それは今現在のブランドの立ち位置だけを見るのではなく、過去があり、未来があり、その上で今がある、と言う視点を持っていることだと思います。今回の審査ではたくさんの刺激を受けました。 石下 佳奈子 Kanako Ishioroshi
石下 佳奈子 Kanako Ishioroshi- 博報堂
クリエイティブディレクター、コピーライター
今年は審査委員のダイバーシティも進み、ますます多様な角度で議論されたのが印象的でした。そのおかげで、議論後に再投票すると激しく上下する作品も現れ、個人的にもハッとさせられることが多々ありました。
また、審査中に自分が「希望」とか「期待」という言葉を普段より多く発しているのにふと気づき、ああ、みなさんの仕事を通してより良く変わっていく世の中にわくわくしているんだな、もっともっと変わって欲しいしそれを楽しみたいんだな、という自分自身への気づきもありました。年々、企業や制作者の正義や覚悟もますます重要になってきています。その正義と、世の中に届ける時の技が見事に決まった仕事の数々が、今回受賞された作品です。おめでとうございます。 イム ジョンホ Jeong-ho Im
イム ジョンホ Jeong-ho Im- mount
CEO、クリエイティブ・ディレクター
同賞の4年目の審査会となりました。例年通り、ひとつひとつの作品を丁寧かつフラットに議論した刺激的な審査会だったと思います。
2日20時間を超える審査の終盤で、とあるプロジェクトに対しておそらく30分を超える議論をしたのがとても印象に残っています。プロジェクトに対して、生きること、つくることのあり方など、非常に幅広く深度のある議論をです。
同賞の入賞は間違いなく価値あることであると、改めて自信を持って言えます。入賞された皆さま、心からお祝い申し上げます。 太田 郁子 Ikuko Ota
太田 郁子 Ikuko Ota- 博報堂ケトル
代表取締役社長 共同CEO エグゼクティブ クリエイティブディレクター
受賞者の皆様、おめでとうございます!初めてこの部門の審査に参加させていただきましたが、「その他」として手口を定義できない仕事が集まるカテゴリーのパワーをひしひしと感じ、次のクリエイティブの道を指し示す名作にたくさん出会うことができました。ブランデッドを冠した部門であるにも関わらず、アンブランデッドなTHE FIRST TAKEがグランプリを取ったのも逆説的で、2020年代のコミュニケーションの可能性を指し示したのではないでしょうか。また、審査委員が多様であることで、ひとつの仕事について多様な観点から批評がなされ、最初は気づけていなかった良さに気づくこともできました。来年も、型にはまらない「その他」な出品を期待しています。
 大八木 翼 Tsubasa Oyagi
大八木 翼 Tsubasa Oyagi- SIXパートナー、バスキュール執行役員
エグゼクティブ・クリエイティブディレクター
誰のために、何をつくり、何処を目指すのか。いち制作者として、そんな根源的な問いを突きつけられる審査会でした。
人生ってどこか永遠につづくもの、と思っていたけれど、ふとしたきっかけで、ほんとうに一瞬で終わってしまうもの。
繰り返される瞬間と永遠のなかで、僕たちは何を残していくんだろう。
その問いに向かう答えを、日々の仕事を通じてひとつひとつ、カタチにしていけたら、と思います。 尾上 永晃 Noriaki Onoe
尾上 永晃 Noriaki Onoe- 電通
プランナー
大体こんな話がなされておりました:誰が何のためにやっているのか?それはブランドのためになっているのか?デジタルにおいて、プロモにおいて、PRにおいて、ソーシャルにおいて新しいか?本気なのか?議論を巻き起こすだけになってないか?それは誰かを幸せにしているのか?何かを前進させるのか?何を変えるつもりなのか?その目的に適した表現や手法をとれているのか?どれだけ変えたのか?いまその課題はどのフェーズなのか(発話が価値があるのか、それとももっと先に行っているのか)?などなど。
個人的には、施策が続くとプラットフォーム化していくという展望に学びがありました。その企画はプラットフォームになりうるかという視点を持つとまた違った考え方が生まれるのかもしれません。 栗林 和明 Kazuaki Kuribayashi
栗林 和明 Kazuaki Kuribayashi- CHOCOLATE
取締役、Chief Content Officer
今年のブランデッド・コミュニケーション部門は、一言でいうと、アツかった。
ソーシャル・インフルーエンスのカテゴリーが新設され、
より一層、これまで評価のテーブルには乗るはずもなかった、異色の仕事が並んだ。
審査委員はきっと、一度は自分が持っている視点で評価し、
そして前提をぶち壊し、もう一度素直に評価する…というプロセスを全作品で踏んだので、
もう全員の脳内がオーバーヒートしていることが目に見えてわかった。
その甲斐あって、本当にたくさんの視点が発掘された。
これも確かに次の広告だ、次のコミュニケーションだ、次の武器だ。
すごく意義のある審査会だった。そして来年は、もっともっとアツくなりそうな予感がする。 小島 翔太 Shota Kojima
小島 翔太 Shota Kojima- 博報堂
クエリエイティブディレクター、CREATIVE TABLE 最高 チームリーダー
とんでもなく疲れました。
多様なバックグラウンドを持つプロたちが丸2日間集まって、本当に丁寧に議論して選ばれためちゃくちゃすごい受賞作です。
そんな視点があるのか、そう褒めるのか、そう言われると確かに、
の連続で、この審査自体が素晴らしく刺激的な場でした。
メディアも手口も次々に増え、生活者の多様な価値観が
可視化されている時代ですが、
それでもやはり「見たことないもの」や「強いインサイトがあるもの」
が人の心を動かす、というこの仕事の根本は全く変わらないんだなと
改めて気付かされました。 嶋野 裕介 Yusuke Shimano
嶋野 裕介 Yusuke Shimano- 電通
zero クリエーティブ・ディレクター、PRディレクター
「激論」という言葉がふさわしい審査会。これほど1つ1つ丁寧に議論する審査は滅多にない。Cカテゴリー(PR)
については「PRとは何か。Cカテゴリー(PR)とは何を評価する場所なのか」についての認識の違いが気になった。単なる「社会的に良いことをした施策」を褒める場所ではないはず。「どんな未来を目指して、どういう結果を出したのか」まで揃ってはじめて評価されるのがこの部門の存在意義。「いいことやりました〜」や、「いいことやったのですが結果はまだです」という応募ビデオが多かったのが残念。ゴールドの中では岩手日報の施策が、グランプリにふさわしいRESULT(記念日の制定)を実現していたと思う。 菅野 薫 Kaoru Sugano
菅野 薫 Kaoru Sugano- 電通
エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター
ここ何年か審査を担当させていただいていて、部門とかカテゴリーってなんなんだろうかといつも悩みます。あえて、「我々」と言いますが、我々(=広告業界周辺でクリエイティブを仕事にしている人たち)【に期待される/が担う】技術が、凄いスピードで【曖昧になっている/拡張している】ということなんだと思います。我々は、いつだってクライアントや社会のために仕事をしているのであって、決して領域のために仕事をしているわけではない。常に、新しい仕事が可能性を広げ、新しい定義をつくる。審査している時点で部門もカテゴリーも古いなって思うくらい、新しい仕事を生み出していかないといけない時代だなと感じています。
 関戸 貴美子 Kimiko Sekido
関戸 貴美子 Kimiko Sekido- 電通
アートディレクター
2年ぶり、2回目のBC部門審査会への参加でした。
今回の審査委員は組織・職種・性別の幅があり、ひとつひとつの応募作品の、「ブランドのためになっているかどうか」という本質的な部分を、多面的な視点で議論したとてもエキサイティングな2日間の審査会でした。
最終的には、各審査委員の専門的視点を超え、個人的な価値観を問われて今回の入賞作品が決まったと思います。
特殊な状況だった2年間で生み出された仕事の数々を拝見し、素晴らしい仕事には、クライアントの意思、クライアントと制作者との信頼関係、目的にあった適切なクラフトが揃っているものなのだとあらためて実感しました。
受賞者のみなさまおめでとうございました。 東畑 幸多 Kota Tohata
東畑 幸多 Kota Tohata- 電通
エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター、CMプランナー
今年の審査会は、例年にも増して、熱い議論が交わされた。事実、あまりの白熱した空気に、本当に酸欠になってしまい、最終審査は、体調不良でBカテしか参加できませんでした。(本当に申し訳ありません)
ブランデッド・コミュニケーションは、もう辺境でも、明後日の広告を発見する場でもない。広告のド真ん中を評価するカテゴリーに成長したと思います。だからこそ、アイデアの新規性だけでなく「時代の記憶になる」「マスターピースになる」仕事なのかを問う視座を持つことが、これからの審査委員には必要なフェーズに突入してきたと感じました。広告クリエイティブを志す人たちの、希望と誇りとヒントになる。それこそが、BC部門のこれからの使命だと思います。 細川 美和子 Miwako Hosokawa
細川 美和子 Miwako Hosokawa- DENTSU
CREATIVE DIRECTOR/COPY WRITER
今まで疑うこともしなかった前提から疑い、それまでの当たり前や枠組みを変えていくブランディングが実現されているのをみて、作り手のチャレンジャー精神に刺激を受け続ける審査会でした。プラットフォームから作ってしまったTHE FIRST TAKE、地方ごとに競い合っていた活性化施策をむしろ各地と一緒にやることで盛り上げようとしている絶メシ、県民の日制定という手法でメッセージを一過性ではなく永続的なものにした岩手日報、エコを説教くさくなく広めるカップニャードル、統合型キャンペーンが賞賛される流れの中、サイトひとつでブランディングをやり遂げたPOLA。次は何を疑えば、新しいものが作れるのでしょうか。でも全てに共通しているのはユーザー発想ということだよなあ。
 細田 高広 Takahiro Hosoda
細田 高広 Takahiro Hosoda- TBWA\HAKUHODO
Executive Creative Director
いいと思うものを、いいと主張する。単純な審査会のはずが、「いまブランドに必要なコミュニケーションは何か?」を問う刺激的な議論に発展していきました。広告の「正義」とは社会にいい影響を与えることか、売りまくってGDPに貢献することか。PRの「成功」とは社会的合意を得ることか、対立させても議論を呼ぶことか。「評価」とは勇気を持って立ち上がったことを讃えることか、最後に転んだことを厳しく公正に判断することか。答えのない問いに、なんとか答えを出したのが受賞リストです。コンテスト以上にコンテキストには価値がある。結果への賛成も反対も。ここから生まれる議論こそがACCの最大成果物だと信じています。話しましょう。
 三浦 崇宏 Takahiro Miura
三浦 崇宏 Takahiro Miura- The Breakthrough Company GO
代表取締役、PR、CreativeDirector
あなたは、信じられるだろうか。19人の大人(それもかなり忙しい)が、2日間に渡り、合計30時間、真剣に議論する空間が存在することを。
ある者は苦悩し頭を抱え、ある者は暴力的なほどに飛沫を飛ばし(マスクしています)、ある者はキング牧師のように自らの夢を語る。
ACC ブランデッド・コミュニケーション部門の審査会は、どんな映画よりもドラマチックな時間だった。
それぞれの価値観をぶつけ合い、この「クリエイティブ」という曖昧な産業の輪郭を手探りで探した。2021年の結論は出た。
この結論が我々の未来をどこへ向かわせるのか、答え合わせはまだ先。来年の審査が、今から楽しみだ。いい仕事しよう。 南 麻理江 Marie Minami
南 麻理江 Marie Minami- BuzzFeed Japan
- ハフポスト日本版/エディター
人間の我儘を無限に許してくれるように思えていた地球が悲鳴をあげ、あらゆる経済活動やこれまでの価値観が急ピッチで見直しを迫られる時代に私たちは立っています。
SDGs、気候変動対策、ジェンダー平等、D&I…。
売上げや利益といったモノサシとこれらとを両立させていく世界線で生きる私たちには、かつてないほどにクリエイティビティが求められます。
“正しいのはわかってるけど簡単じゃないんだよ… ”
審査を通じて目にしたのは、ビジネスが抱えるこうしたジレンマを乗り越えていく卓越したクリエイティブのパワー、パブリックリレーションズの可能性でした。
橋田審査委員長と皆様に感謝いたします。必ずここから、未来を変えていけると確信しています。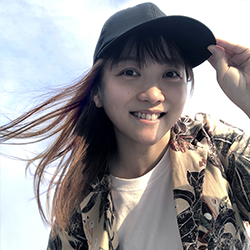 村上 絵美 Emi Murakami
村上 絵美 Emi Murakami- ADKクリエイティブ・ワン
クリエイティブディレクター、アートディレクター
BC部門は、お仕事の大小は関係なくブランドに対してどれだけ真摯に丁寧に、本気で、愛を持って向き合ったかの勝負だと感じました。審査委員もその愛にこたえるべく、最終審査会は全員が脳みそフル回転で激論に激論を重ねた、アツい2日間だったと思います。各ジャンルの精鋭たちが審査するのですから、どんな小さなことでも良いところは逃さず見つけてくれますし、逆に作品を良く見せたいが故の嘘があったり、真摯さや愛が足りない作品は即見抜かれますのでお気をつけください。今回初参加させていただきましたが、広告の未来を背負って臨まれている皆さんを目の当たりにして、私にとっても明日への活力になりました。ありがとうございました!
 村山 佳奈女 Kaname Murayama
村山 佳奈女 Kaname Murayama- 博報堂ケトル
ディレクター、編集者
昨年、ブロンズをいただいた際に「メダルの色は関係ない」と、言葉をかけられました。すみません……当時の私はこれ、綺麗事だと思っていました。でもどうやらほんとうに、そこはあまり重要じゃなかったな、というのが今年、審査の場に呼んでいただいての実感です。便宜上ランクはつけられますが、第一線で活躍する審査委員の方々が、朝から晩まで議論し、ヘロヘロになりながら絞り込んだ入賞作品群はいい意味で微差! 残った作品はすべて偉大だと感じます。議論の詳細はぜひ議事録にて。最後に、今年、審査委員のダイバーシティ方針を打ち出してくださったACCの皆様に感謝します。
- HASHI
-
デザイン部門
審査委員長 永井 一史 Kazufumi Nagai
永井 一史 Kazufumi Nagai- HAKUHODO DESIGN
代表取締役社長
昨年できたばかりのカテゴリーということもあって、
ACCとしてのデザイン部門のあり方の確立も意識しながら審査を行った。
前年度の審査後、“我々が評価したものは果たして何だったのか?”という振り返りで、
カタチだけではなく、そもそもの目的や今後の可能性も含めて評価していたのではないか、
それは言わば”プロジェクト”とも呼べるのではという議論をした。
今年度は、その枠組を審査メンバーと事前にしっかりと共有しながら審査に臨むことができた。
結果、多様性がありながらもACCのデザイン部門として軸のぶれないものが選ばれたと思う。
入賞したものはどれも素晴らしかったが、個々の評価については、
新たな試みである審査評をご覧いただきたい。
優れたものに光を当て、社会に共有されることがこの賞の目的である。
しかしその先に、様々な課題に対してデザインに何ができるのかの可能性を示し、
優れたプロジェクトが次々と生まれるきっかけになるような場所になれればと願っている。デザイン部門
審査委員 アストリッド クライン
アストリッド クライン
Astrid Klein- クライン ダイサム アーキテクツ
建築家
今年のACC賞のデザイン部門で上位に入った候補者たちは、いずれも社会の中で人々の生活をより良くしたいという、意味のある目標を掲げていることが共通しています。審美的視点でただ美しいデザインにふけるのではなく、スマートなデザインソリューションを必要とする問題の核心を把握しようとする試みが表れていました。これは非常に新鮮なことであり、今後、魅力的ではあっても単に再パッケージ化されたデザインを大量に生み出すようなものではなく、目的をはっきり持った質の高いデザインが候補作品にあがってくることを期待させてくれました。
また、今回の審査委員はさまざまなスキルを持ち、多様なバックグラウンドを持つ女性が中心に構成されていました。社会を良くするためには、男女のバランスがとれていることが理想的ですが、個人的には多くの女性の声が明らかに共感に影響を及ぼしているのを聞くことができ、何度も感激を覚える審査会になりました。 上西 祐理 Yuri Uenishi
上西 祐理 Yuri Uenishi- アートディレクター、グラフィックデザイナー
デザイン部門の審査を複数年担当していますが、
毎年「デザイン」とは何なのか、考えさせられながらの審査です。
今年は昨年よりさらにプロジェクト型の仕事が多くの受賞をし、
社会的意義や継続性、必然性がより重要視されたのではないかと思うし、
そういうもので溢れた世の中であって欲しいと願う。
一方で、純粋な作る喜びに溢れたもの、身体が反応してしまう美しさ、
専門性から生み出されるプロの視点や発見や技術など、
そういうクリエーティブの「楽しさ」も改めて大切にしたいと思う。
多様な仕事が競う部門だからこそ、評価がとても難しいのだが、
どちらの良さも大切にしていきたいと改めて思う審査でした。 川村 真司 Masashi Kawamura
川村 真司 Masashi Kawamura- Whatever/Chief Creative Officer、Co-Founder
- WTFC/Chief Creative Officer
審査委員も、受賞作も、とても多彩で楽しい審査会でした。昨年からデザイン部門の審査委員を務めさせていただいてますが、ACCのデザイン部門ならではの「デザイン」解釈や評価軸がさらに洗練されてきている気がしました。その軸をもとに、表面的な意味でのデザインではなく、その手前の取り組み自体の構造からきちんとデザインされているものが評価されたと感じています。来年以降も、このコンセプトを守って、さらに強度のあるデザインを評価できるようこの部門を進化させていって欲しいと思います。
 小杉 幸一 Koichi Kosugi
小杉 幸一 Koichi Kosugi- onehappy
アートディレクター、クリエイティブディレクター
「デザインはプロジェクトへ」。新デザイン部門1年目の経験により、永井審査委員長から審査委員全員に事前にそういった意識で審査しようと共有してもらいながら、臨ませていただいた2年目。結果、「プロジェクト」といった視点でみた受賞作品の優位性とは、対象に向けた<寄り添う>力の解像度の高さであり、深度であったと察する。「プロジェクト」とは時間軸を想起するところもあるが、要は静的で関係性が閉じて共感されないものでなく、社会性や時代性に敏感にその課題の本質を捉え、そこから見たこともないクリアなアイデアとしてのクリエイティビティがあるか否か。さらに巻き込む力があるか。<寄り添う>という情熱を持った姿勢や視点、意識があればそれは必然的に静的ではありえない。自ずと動的に世の中を動かす力になるに違いない。ACCのデザイン部門だからこそ評価できる視点は、この圧倒的で丁寧な<寄り添う>力なのかもしれない。
 柴田 文江 Fumie Shibata
柴田 文江 Fumie Shibata- Design Studio S/代表
- プロダクトデザイナー
今年度はACC審査会にはじめて参加させていただきました。最初に嬉しかったことは審査委員のジェンダーバランスが取れていたことです。新しいデザインの方向性を審議するこのような会であってもこれまでは偏りがあったので、まずそのことに触れておきます。広告やデザインは世の中の価値観を牽引する力があるので、ここでのジャッジが社会のダイレクションになるという意識を持って、フラットで親切丁寧な議論が交わされていました。ACCの中でデザイン部門が担う役割は、新しいクリエーションを作る側よりも受ける側に立ち考えることのように思います。それによって未来の広告やデザインがより力強いものになることを期待しています。
 高橋 理子 Hiroko Takahashi
高橋 理子 Hiroko Takahashi- アーティスト
デザインという言葉の既存認識の範疇では審査できないほどジャンルレスな応募作品に向き合うために、心を開放して臨んだ審査。さまざまな分野から集まった審査委員の知識や経験のピースを組み合わせ、時には直感も大切にしながら、議論を重ねた審査会は大変刺激的でした。最終的には、どれだけ人の心に響き、記憶に刻まれるか否かが重要なのだということ。社会にとって、そしてこのACCデザイン部門にとっても、意義のある作品を選出できたのではないかと感じています。引き続き、時代の空気をまといながらもそれに囚われすぎず、強い信念を感じる作品の誕生を期待しています。
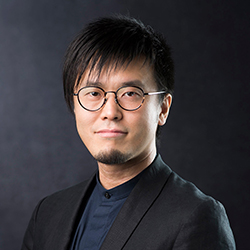 太刀川 英輔 Eisuke Tachikawa
太刀川 英輔 Eisuke Tachikawa- NOSIGNER/代表
進化思考家、デザインストラテジスト
慶應義塾大学/特別招聘准教授
昨年誕生したACC賞デザイン部門。第一回の審査総評において、この賞はプロジェクトとしてデザインを観ている、という言葉が頭に浮かんだ。これは現在のデザインにとって本質的テーマとも重なるだろう。もはや私たちはデザインを専門領域ではなく、美しい未来の可能性を示す方法として見始めているのだ。
しかし本賞はビジネスアワードではない。プロジェクトのデザインがもたらす美しさや感動、心に訴える創造性が宿っているか。それがこの賞が投げかける視点だ。
社会は心の動きの連鎖によって変わる。それを生み出すのは創造性に他ならない。今年もまた応援したいと純粋に思えるプロジェクトたちを評価し、その背中を押せたことを喜びたい。 林 千晶 Chiaki Hayashi
林 千晶 Chiaki Hayashi- ロフトワーク
取締役会長
広告という領域の中で、デザインが示す領域は何なのか?それを問わざるを得ないと思っていた。でも蓋を開けてみると、はっきりと言語化されていないにも関わらず、上位をしめるプロジェクトは、審査委員みんな似通っていた。「格好いいけれど、一時的に生み出されたもの」ではなく、「未来に向けて続いてほしいもの」「一人にどれだけ深く伝えられるかを問いただしたもの」を考えるプロジェクトに、票が集まっていたように思う。そういう意味では、見かけの良さよりも、作り手の真摯さや情熱が問われるようになったのだ。嘘は通用しない時代になったことを、痛感した審査会だった。
 原田 祐馬 Yuma Harada
原田 祐馬 Yuma Harada- UMA/design farm/代表
- どく社/共同代表
 ムラカミ カイエ Kaie Murakami
ムラカミ カイエ Kaie Murakami- SIMONE
CREATIVE DIRECTOR
昨年に続く審査会参加でしたが、今年は更に多様化した審査委員の面々による幅広い視点、
専門性に富んだ鋭い考察、審美眼からの学びが多く、とても勉強になりました。まだ
2年目の新設部門ということもあり、応募点数が少ない傾向にはありますが、高い熱量や
想いを起点に社会を前進させようとする受賞作が増え、着実に前に進んでいる印象を受けました。
とはいえ、この分野が大量生産消費社会との結託によって成長し、同時にその功罪の一端を担ってきた状況に変わりありません。デザインに関わる多くの人々が、これまでの歴史を反芻しながら複雑化した社会をより解像度高く直視し、本質的な社会変革を促すエントリーが増えることを期待しています。 ライラ カセム Laila Cassim
ライラ カセム Laila Cassim- シブヤフォント/アートディレクター
- 東京大学先端科学技術研究センター/特任助教
広告はデザイン領域と同様、根元の軸に「伝える」と「届ける」があります。これまでは「マス」に向けて出来上がった商品やサービスの認識に活用していたものが、今では「マス」という考えも分散し、社会というものは一つではなく様々な価値観を持つ人々でできていることが可視化されました。デザイン領域での手法や考えはここ十年程で急激に変わり、広告も単に「もの」を伝えるだけでなく「価値観」を伝えることにシフトしました。今回の審査で感じたのは元々は独立していた広告という専門性が様々なデザイン分野の制作と現場にチームの中に溶け込みその価値を伝えようとしていること。
広告、プロダクト、サービスデザインや建築であれ、どのエントリーも私たちが住む世界の「人」「時代性」と「生活」を軸に考え「伝える」「届ける」ことを大事に作っていたように思えます。これからも様々な専門性や立場の人たちがデザインを通してコラボし私たちの生活の発展に促進していけるような世の中になって欲しいなと素直に願います。 - HAKUHODO DESIGN
-
メディアクリエイティブ部門 審査委員長
 中谷 弥生 Yayoi Nakatani
中谷 弥生 Yayoi Nakatani- TBSテレビ
総合編成本部 DXビジネス局長
メディアクリエイティブ部門史上、最高点!!5人の方が9点をつけた圧倒的なグランプリでした。
「THE FIRST TAKE」は音楽業界において生のライブが中々できない閉塞感の中で、新しい境地を開いた作品でした。音楽映像と言えば、我々テレビ局を含めて、これまでメディアは演出されたカメラワークに編集を尽くした完成品をお届けしていました。今回の「THE FIRST TAKE」はそんな常識・前提を覆した中での「音楽の可能性の発明」であり、素晴らしい「アートワーク」で、皆が出演したい「メディア」を創造しました。
「共演NG」もまさに「前提を疑った」作品。競合スポンサーは中々同居しない「業界の常識」を覆し、そんな業界ルールを笑い飛ばすように、閉塞感を打破した作品でした。
その他も「斬新なアイデア」に加えて、「本当に効果があったのか!」など喧々諤々議論し、全員で選びつくした作品ばかりです!メディアクリエイティブ部門 審査委員
 有元 沙矢香 Sayaka Arimoto
有元 沙矢香 Sayaka Arimoto- 電通
コピーライター、プランナー
昨年から引き続いて審査をさせていただき、その変化がとても面白かったです。昨年はyoutbe、SNSなどデジタルメディアを使い倒した作品がグランプリ。今年はそこに新しいプラットフォームを作った作品がグランプリ。TikTionary、野田ゲーや絶メシもそうですが、これからそうしたみんなが乗っかっていけるアイデアがどんどん育っていくんだろうなと思います。一方で、雑誌『広告』やおみやげ防災のようなピンポイントだけれど深度のあるコミュニケーションもメディアとの掛け合わせならではだと思うので、応援していました。いずれにしても骨太なアイデアが必要なので、いち制作者としては身の引き締まる思いでした。
 石井 うさぎ Usagi Ishii
石井 うさぎ Usagi Ishii- Google
Executive Creative Director
オンラインでの審査でしたが、各審査委員が様々な視野やアプローチ方法を持ち寄り、丁寧にディスカッションを深めることができたと感じています。
そういった中で議論が集中したのは、今の時代の「メディア」をどう定義づけたらいいのだろうか?そしてコロナ禍におけるオンライン生活環境や生活者の最新メディアインサイトなど、様々な変数が入りこんでいる中でのメディア的チャレンジをどう評価するべきか?ということでした。
辿り着いたのは「それでも人が集まり、思いを共にし、心を揺さぶられ、結果として態度変容に深く寄与する場づくり」ができている、前例のないところに切り込んでいく仕事は光り輝き存在感を放つ、ということでした。 今西 周 Shu Imanishi
今西 周 Shu Imanishi- 日本コカ・コーラ
日本・韓国オペレーションユニット、マーケティング本部IMX(インテグレーテッド・マーケティング・エクスペリエンス)事業本部長
私は今回初めてACC賞の審査会に参加させていただきました。新設から5年目のメディアクリエイティブ部門ということですが、クリエイティブアイディアとその効果を最大化させるメディア活用の統合的なプランニングは、確実に購買やアクションにつなげるために消費者とのエンゲージを深めるコミュニケーションや体験を届けていく上で近年その重要性は増していると考えています。よって、審査会では各審査委員の専門領域を背景としたコメントや熱意ある評価ポイントを伺うことができ、大変刺激をいただくことができました。
 内田 佳奈 Kana Uchida
内田 佳奈 Kana Uchida- ライオン
ビジネス開発センター エクスペリエンスデザイン マネージャー
昨年のエントリーは、コロナ禍で人が出歩かない・人と接触できない状況で“どうやって広告を届けるか”という点に工夫が凝らされた企画が多くありましたが、今年はその状況から一歩進んで、“メディアがそもそも持っているアセットをどうやってフル活用するか”という視点の企画が増えた印象でした。そのなかでも、「敏腕プロデューサーによるクライアントの巻き込み方」がポイントだったと思われるものや「メディアの通常の使い方を良い意味で裏切る」ことがポイントだったものなど、多種多様な方面からメディアの未来を見通す審査会となりました。これらの企画に賞が授けられることで、常識的ルールに縛られないプランナーや広告主が一層増えることを期待しています。
 榊原 誠志 Seiji Sakakibara
榊原 誠志 Seiji Sakakibara- テレビ朝日
ビジネスソリューション本部 コンテンツ編成局
総合編成部長
今回は初めて「メディアクリエイティブ」部門の審査に参加させて頂きました。
100を超える刺激的な作品に出会えたことはとても感謝しております。
審査している間、メディアクリエイティブとは何かを常に自問自答する時間でした。
そして様々な作品に触れるたびに自問自答の振れ幅がどんどん広がっていく。
そんな不安を抱えながら審査委員の方と議論していくと、個性的で多様な議論が交わされる中で
少しずつ「結局面白い、気になる仕掛け」が混とんとした世界では光るのかなと思いました。
やはりメディアは面白い。改めてそんなことを考えさせる作品に出会えて幸せでした。 田中 美奈子 Minako Tanaka
田中 美奈子 Minako Tanaka- 博報堂DYメディアパートナーズ
クリエイティブディレクター、メディア・コミュニケーションプロデューサー
今年は印象的なことが2つ。
1つは「FIRST TAKE」の審査での議論。
つべこべ語らずとも満場一致のNO1!で、審査委員全員で向き合う問い。
どこがメディアクリエイティブとして優れているのか?
「今までにない音楽番組フォーマット」「メディア=人が集まる場を作った」
「完成されたものを見せるテレビやデジタル文化に一石を投じた」
多様な意見が、まさに部門の象徴のようなグランプリでした。
2つ目は、許すクリエイティブの力。
クリエイティブはどうあってもポジティブであるべきと信じてきました。
が、2021年という年は形が違ったのかもしれない。
悲しみや諦め、人への恨みや妬み、弱い自分、弱さを受け入れられない自分。
そんな捨てきれないものを許す優しさも、必要だった。
陰は、強すぎる光から私たちを守り癒します。
その感覚を落とし込んだクリエイティブに、私自身も癒され感動しました。
これも時代性。メディアクリエイティブは、やっぱりおもしろいですね! 秀島 史香 Fumika Hideshima
秀島 史香 Fumika Hideshima- FM BIRD
ラジオDJ、ナレーター
同じ作品を前にした時、人の感じ方はこうも違うものかと、特に今年は強く感じました。なにを今さら当たり前のことを…ですが、気づいたら自分にとって居心地の良い固定観念にすっぽり入り込んでしまい、「これが世の中の相場だろう」と思い込んでしまう危うさも増しています。価値観も多様化していく今、メディアはどんな一石を投げられるのか。その一石が、どんな対話のタネになれるのか。心を射抜かれるような作品、審査委員の皆様の言葉に、ハッとウロコが落ちたり、じわじわ理解が深まったりと、モノの見方を拡張してもらえる刺激的な体験でした。これからも、柔軟に伸ばしていかないと。
 平井 孝昌 Takamasa Hirai
平井 孝昌 Takamasa Hirai- ADKマーケティング・ソリューションズ
エクスペリエンス・デザインセンター
バーティカル・プランニング・ディレクター
審査にあたり自分自身の審査基準はなんだろうか?それを事前に書き出していたのですが、広告会社や事業会社、そしてメディア会社の皆様の評価を聞くことでその基準をブラッシュアップ、そして全体基準へと、審査会を通じて一段上の視点を考えることができたのが印象的でした。
メディアクリエイティブはメディアという容れものへのアイデアが問われるカテゴリーですが、何をもってメディア、容れものとするのか?この議論がとても白熱し、自分も含めて、審査委員の方々の意識のアップデートを図れたような気がします。
これもひとえに素晴らしいエントリーに恵まれたからだと思います。全エントリーに敬意を表したいと思います。 前田 淳子 Junko Maeda
前田 淳子 Junko Maeda- 電通
ソリューションクリエーションセンター
エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター
メディアに携わるお仕事という共通点はあっても、それぞれ各分野の第一線で活躍されている方とのセッションをとても楽しみにしていました。皆さまの考察力には「このような見方があったか」と思わず画面越しに唸ってしまう事が多々ありとても刺激的で学びが多い一日になりました。
作品については、コロナ渦の中でどう世の中にメッセージを送り、接点を持つか。影響を与えていくか。という事を熟考した作品が評価を得られていたのではと感じました。
これからも、日々変化がある中で、常に多様な姿勢・視点を持ち、ターゲットの心の内をくみ取りながら企画を構築・実行していく柔軟性が益々必要になってくると感じました。 宮道 治朗 Jiro Miyamichi
宮道 治朗 Jiro Miyamichi- フジテレビジョン
編成制作局 アナウンス室 局長職 兼 室長
面白かったですねー。皆さんの「推し」の感性が多様で。時に全然共感出来ず(笑)でも後で納得もあったりして、それがまた楽しかった。
僕は全て直感で決めました。で、決めた後に何が良いと感じたのかをロジックにしました。この作業がいつも勉強になるので好きです。
メディアクリエイティブ部門は一番幅の広いカテゴリーですよね。エントリー作品の多様性は審査を難しくしていたけれど、メディアの過渡期をそのまま反映した面白いラインナップになっていたと思います。このカオスは企画者や制作者たちが抱く「変化への挑戦」や、逆に「変わってはならない普遍」の両方を内包していて、どちらにせよ「思い」に溢れていたと思います。凄く刺激を受けました。 横山 祐果 Yuka Yokoyama
横山 祐果 Yuka Yokoyama- ABEMA
プロデューサー
審査に関わらせて頂いたこと、大変光栄に思っております。創意工夫がこらされたエントリー作品の新しい挑戦に出会う度、ワクワクが止まりませんでした。審査会では、様々な立場の皆様からのご意見を伺うことで、たくさんの視点を持つことができ、本当に勉強になりました。
審査をさせて頂く中で、個人的に心にとまった作品に共通していたのは、長引くコロナ禍において『みんなが集まれる場所』を生み出すことに成功している作品でした。新しいアイディアで、思わず人に言いたくなる仕掛けを作り、多くの人と熱狂を分かち合える体験を提供する。素晴らしい作品に唸らされ、感謝の気持ちでいっぱいです! - TBSテレビ
-
クリエイティブイノベーション部門
審査委員長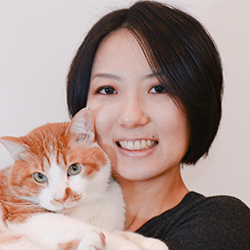 米澤 香子 Kyoko Yonezawa
米澤 香子 Kyoko Yonezawa- Wieden+Kennedy Tokyo
Creative Tech Director
まずはご応募いただいたみなさま、ありがとうございました。本年度の応募作品はどれも本当にレベルが高く、いままでで一番審査も白熱したように感じます。超高齢化社会へ向かう日本に救いの手を差し伸べるようなアイデア。誰もが自分らしく活躍できるようになる仕組みの創造。新しい世界的な文化創造の試み。誰もが試してみたい!と思ってしまう斬新なプロトタイプ。既成概念に新しい角度から光を当てるプロジェクト。この国の未来を形作る、その礎となり得るような意欲的な作品が多数ありました。
グランプリを受賞した3D都市モデル整備・活用・オープンデータプロジェクト “PLATEAU(プラトー)” は、その中でも特に異彩を放っていました。かつて伊能忠敬によって日本地図に革新が起こったように。都市計画や防災からエンタテインメント、更には新規ビジネスの誕生を予感させるデータ群。首都圏だけでなくさまざまな市町村にどんどんと広げていく浸透力。利用促進のためのさまざまな活動とコラボレーション。デジタル・トランスフォーメーションとは斯く起こすべしという手本のような鮮やかな手腕でした。イノベーションとは規模の大小に関わらずどんな場面にも起こしうることですが、この時代に国家発でこのようなプロジェクトが生まれたことに希望を感じます。クリエイティブイノベーション部門 審査委員
 岩下 恵 Kei Iwashita
岩下 恵 Kei Iwashita- IDEO Tokyo
Design Director
そもそもクリエイティブ・イノベーションとは?
この部門はすでに事業化されているサービスから、アイデアを形にしたプロトタイプまで、幅広い作品をカバーしている。正直比較するのは難しい。
そこでいつも立ち戻るのは、審査基準のひとつでもある「未来を創れるようなポテンシャルを有しているか」。
良いアイデアだけでは、イノベーションは起こせない。
試行錯誤を通じてはじめて、本当に社会に根付く・人の生活を変えうるモノを創ることができると思っている。
今年の入賞作品はここに至るまでの学びや苦労、そしてコンセプトの進化が見れた。
受賞をきっかけに、今後の更なる成長を願っている。 小野 直紀 Naoki Ono
小野 直紀 Naoki Ono- 博報堂
『広告』編集長、monom代表
一番印象に残っているのはグランプリを獲った国土交通省による「PLATEAU」。国が民間の賞レースに入ってくることの是非はあるかもしれないが、個人的には是だ。よりよい生活や社会のためのプロジェクトが、国なのか民間なのか、企業なのか個人なのか関係なくフラットに応募される。そんな賞のあり方は、とても今っぽいのではないだろうか。そして評価され応援されるべきは、国や企業といった大雑把な単位ではなく、そのプロジェクトを推し進める熱と志を持った人たちだと思う。受賞された皆さま、おめでとうございます。
 木下 真吾 Shingo Kinoshita
木下 真吾 Shingo Kinoshita-
NTT人間情報研究所/所長
大阪芸術大学 アートサイエンス学科/客員教授
電通 Dentsu Lab Tokyo/客員主席研究員
今回の審査にあたり、私が考えるイノベーションの定義は、"Innovation is the implementation of creativity"でした。
今回の受賞作品は、まさにこれに当てはまるものが多かったように思います。
グランプリのPLATEAUは、次世代の社会インフラとなりえる立体地図を、誰でも使えるようにするというアイデアに対し行政が全力でスマートに推進し、ゴールドのAlonAlonフラワープロジェクトもHelppadも、困っている方に寄り添い最初から100点を狙わず、でも、しっかり幸せになるアイデアを、地道に社会実装していました。
こうした、素敵なアイデアと社会実装力を源泉とするイノベーションが、この賞をきっかけに広がっていくことを期待します。 キリーロバ ナージャ
キリーロバ ナージャ
Nadya Kirillova- 電通
クリエーティブ・ディレクター
「クリエイティブイノベーション」のカタチは無限に存在し、モノやビジネスになっていなくても、ちょっとした一言やアイディアや作戦やコンセプトで世の中がガラッと変わってしまうことがある。今年は、より広い範囲にイノベーションの定義を広げたことで、昨年多かった広告業界発のイノベーションからプロダクトや事業へとシフトしたエントリーが多かった印象だ。我々の人生をより豊かにハッピーにするものが多くあったことが特にうれしい。一方、「しっかりビジネスになっているか?」という基準がやや強くなってしまったことで、「クリエイティブ」の部分が少し薄まったこと、またビジネスとは異なった顔つきをしたイノベーションとその「タネ」を拾えなかったのが少し心残りだ。
 徳井 直生 Nao Tokui
徳井 直生 Nao Tokui- 慶應義塾大学/准教授
- Qosmo/代表取締役
- Dentsu Craft Tokyo/Head of Technology
今年の応募作品、特にファイナリスト以上に選ばれた作品には、障害者や介護が必要な高齢者などの社会的に弱者される方々やそうした方々を支える人々に手を差し伸べるプロダクト、サービスが目立ちました。これまでどちらかというと大文字の創造性の実現(種としての人類全体にとっての未知の領域)を希求してきた先端テクノロジーの目線が、個々人の創造性や心の豊かさの実現にも向けられるようになってきた。そんなポジティブな変化を感じました。一方で地球環境に関連するプロジェクトがあまり見られなかったのが個人的には気になっています。その辺り、来年以降に大いに期待したいと思います。
 中西 裕子 Yuko Nakanishi
中西 裕子 Yuko Nakanishi- 資生堂
R&D戦略部 R&D戦略G
資生堂オープンイノベーションプログラムfibonaプロジェクトリーダー
今年も数多くの素敵な作品がエントリーされ、こんな人への眼差しをもった商品やサービスが増えたら、世界はきっともっとより良くなるに違いないと、審査中、実感する機会が多々ありました。さらに、「今迄のあたりまえを疑う/変える」アイデア、そのスケールの大きさや人へ与える影響の深さ、そしてその達成度を作品ごとに感じ取っていたように思います。
PLATEAUのように今までの地図の概念を根底からテクノロジーの力で変えるもの、AlonAlonフラワープロジェクトのように、とある人の人生にひっそりと、しかし確実にテクノロジーが寄与しているもの、そして、味わうテレビ TTTVのようにテクノロジーを駆使して実物を作ってみたからこそ、発展性に対する妄想を掻き立てられるもの。
奇しくもこの部門の名称である「クリエイティブ」とは、「イノベーション」とは何かを自問自答し、さらには他の審査委員の方々とのディスカッションを通じてその認識が深まり、この賞の意義を改めて実感した審査会でした。 中村 洋基 Hiroki Nakamura
中村 洋基 Hiroki Nakamura- PARTY/Creative Director、Founder
- ヤフー/MS統括本部 ECD
おかしい。
この部門だけ、なんかおかしいぞ。
ぼくの知る広告アワードの審査は、広告としてイケてるとか、視点やインサイト、表現やリザルトについてやいのやいの議論する場のはずだ。
なのに、この部門ときたら。VCが事業性について指摘し、プロダクトデザイナーが、クラウドファンディングで0次流通に成功したプロダクトの完成度を評価し、編集長が日本のデジタルツインの可能性について示唆し、大学教授が価値を再定義する。この部門で受賞することは、資金調達やピッチイベントよりよっぽど難しいのではないか?政府の投資部門かと。
それでいて非常にフェアで清々しい雰囲気なのだ。
今年はLUUPやHelppadのような、ガチのスタートアップも応募し始めました。なんというか、風を感じます。化けますよ、この部門は。 福原 志保 Shiho Fukuhara
福原 志保 Shiho Fukuhara- グーグル/テクノロジーインテグレーションリード
- bcl
- HUMAN AWESOME ERROR
昨年からACCの審査会に参加させて頂き、去年に比べて、働き方のイノベーションなど、テクノロジーと広告に寄っていた昨年から、当事者視点や、生活者視点で、リアリティのある試みを感じるエントリーが増えました。
ただ、完成しきっていないプロトタイプにも物事の捉え方を変える要素、可能性があると思います。
来年は寛容さや個人の弱さを汲み取る社会的な課題に寄り添うようなエントリーを期待して、今年の審査が繋がれば良いと願っています。 坊垣 佳奈 Kana Bogaki
坊垣 佳奈 Kana Bogaki- マクアケ
共同創業者・取締役
今年のクリエイティブイノベーション部門の審査は、世界がコロナによる日常を新しい日常と捉え、その中で少しでも世の中が明るく・良くなるようにとそんな思いをのせたたくさんの応募から始まりました。その結果としてのグランプリ・ゴールド・それに続く受賞作品は、それを大いに反映したものになったと思います。
地球の課題は人類の経済発展とともに大きくなる一方ですが、それになんとか争おうとする想いとアイデアの数々が、今世界を動かそうとしています。この時代において評価されるべきイノベーションは、課題認識とそれに対する強い想い、それを解決するための根気強い歩みによってしか起こらないのだと、改めて感じる審査会となりました。世の中を良くしたいと願うイノベーションの種である全ての応募作品に敬意を評して。このような機会をいただき、ありがとうございました! 松島 倫明 Michiaki Matsushima
松島 倫明 Michiaki Matsushima- 『WIRED』日本版
編集長
身体的な障害をもつ方や移動が困難な高齢者など、これまで社会の一元的なシステムやプロダクトでは届かなかった人々に向けたエントリー作品が多く揃い、より多様な視座をもつ方々によるイノベーションの民主化が加速していることに勇気づけられる審査会だった。一方で、時間と距離の制約を乗り越えるという人類の根源的な欲望に応えるエントリー(宇宙、都市、そして味!)も、突き詰めれば同じ社会的ミッションの延長にあって、今後さらなる融合がこのクリエイティブイノベーション部門で起こるはずだ。
 矢澤 麻里子 Mariko Yazawa
矢澤 麻里子 Mariko Yazawa- Yazawa Ventures
Founder and CEO
今回は、クリエイティブイノベーション部門の審査委員として3回目の参加となりますが、以前にもまして、いろんな要素がぎゅぎゅっと詰め込まれて魅力的な応募作品ばかりでした。
特に、SDGsの流れも受けてか、一口に「クリエイティブ」「技術」「イノベーション」で括れない社会意義の高い作品も多く、審査会においてディスカッションも活発になり、審査の難しさと面白さ感じました。
その中でも、ファイナルに選ばれた作品はどれも素晴らしく、5年後・10年後の当たり前になっていることを感じさせられる納得のいくものばかりだと思います。
「ACCを見れば、未来がわかる。」そんな言葉がぴったりなACC審査会だったと思います。 暦本 純一 Jun Rekimoto
暦本 純一 Jun Rekimoto- 東京大学/教授
- ソニーコンピュータサイエンス研究所/副所長
ACCクリエイティブイノベーション部門では、既に製品になっているものから、まだ研究開発途上のものまでを幅広く審査するというところが特徴です。性質が異なる応募作品をどのようにして公平に審議するかが毎年課題になっています。全体の傾向として、単に面白い技術を開発しました、というだけではなく、どう利用されるか、社会にどのように根付いていくか、どういう未来を作っていきたいのか、までを深く考えられている作品、世界観のある作品、が多かったと思いますで。ただ、個人的にはそういう「立派な」応募作品だけではなく、はっちゃけてしまったり斜め方向にとがってしまっているような作品も応援していきたいと思っています。
- Wieden+Kennedy Tokyo





今回の審査では「今までの当たり前を変えているもの」を評価してほしい、と審査委員のみなさまにはお願いしました。メッセージや映像や手法や枠組みなどを通して、今までになかった視点をくれて、広告の可能性を少しでも広げ、その歴史を更新しているものを見つけ、評価していけたらうれしい、とお伝えしました。そのため審査委員の人選も、性別はもちろん例年より幅広い世代、職種、所属先を意識し、選ぶ方の視点にも広がりを目指しました。おかげさまで審査は紛糾を極め、この広告を賞に選ぶことはどんなメッセージなるのか、という点はもちろん、そもそもの審査の仕組みや賞の存在意義にまで議論が及ぶ忌憚のない白熱した会になりました。翌日夕方まで寝込みました。今後の参考になりそうな議論はフィルム部門としては初めての議事録として残し、ダイジェストにはなってしまいますが公開します。そして今後ACCが広告の未来により役立つような賞になるためにも、活かしていけたらと思っています。選ばれた受賞作はどうでしょうか。みなさんの生きていく視点を、そしてこれからの広告の可能性を、広げてくれるものになっているでしょうか。聞かせてもらえたらうれしいです。