- TUGBOAT
クリエイティブディレクター・CMプランナー
2020 60th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS 審査委員講評
-
フィルム部門 審査委員長
 多田 琢Taku Tada
多田 琢Taku Tadaフィルム部門 審査委員
 麻生 哲朗 Tetsuro Aso
麻生 哲朗 Tetsuro Aso- TUGBOAT
CMプランナー・クリエーティブディレクター
久しぶりの審査会参加だったが、各審査委員の見解を聞きながら、色々な価値観があると改めて感じた。それぞれが「何を」評価するのか、視点は一定ではない。そんな議論を経て、賛否が飛び交う中でそれでも突き抜けてくるものが賞を取るというのは正しいし、そうなるよう委員長が丁寧に議事を進めてくれていた。フィルム部門だからか、オンライン審査のストレスは疲れ以外さほどなく、妙に場の雰囲気が出来上がったりもせず、むしろ年代、職種を越えてフラットに向き合えていた感じがした。「今、ここからどう抜け出そうか」そんなそこはかとない世の気分をキャッチアップしたかのような2本が最後を争ったのは、今年だからこそではないかと思う。
 尾形 真理子 Mariko Ogata
尾形 真理子 Mariko Ogata- tang
クリエイティブ・ディレクター/コピーライター
2020年の「視点」をどう反映するか?
「自分の価値観で正直に審査を」という多田さんの審査方針を聞いたとき「それなら明確だ!」と思ったのに、いざ審査をしてみると…。2020年は作り手として自分の価値基準が大きく揺さぶられる状態で、事前審査の段階でも己の評価基準に自信が持てず、ものすごい気が重いまま最終審査に参加しました。
コロナ前とコロナ後が混在する審査で、フィルム部門としての評価をどう考えるか。異なる価値観を擦り合わせるのではなく、ひとつの流れを作るのでもなく。それぞれに意見を言って、聞いて、考える。多様な賛否があるままに議論を重ねた先にあったもの。それは現状に囚われず、現状を打破していく、そんな希望を感じるという「視点」であったように思います。 川腰 和徳 Kazunori Kawagoshi
川腰 和徳 Kazunori Kawagoshi- 電通
クリエイティブディレクター/アートディレクター
審査委員初体験で、貴重な経験をさせていただきました。順位の決まり方を特等席で見させていただいているような感覚でした。こんな真剣に、こんな丁寧に、こんな公平に。若造の意見もちゃんと聞いてくれるフラットな場所でした。ファイナリストになることすら、すごいですが、メダルを獲るって本当にすごいことなんだと、改めて思いました。今年は運良く審査委員として呼んでいただきましたが、自分はまだまだ審査するような立場ではありませんので、チャレンジャーとして来年こそはフィルム部門で勝負できるような作品をつくって審査委員のみなさんと、世の中の度肝抜いてやろうと思ってます!ありがとうございました!受賞者の皆様おめでとうございます!
 神田 祐介 Yusuke Kanda
神田 祐介 Yusuke Kanda- 博報堂
クリエイティブディレクター/CMプランナー
グランプリを“決める”というより、“送り出す”感覚。初めてのACC審査の場で気付かされた自分が想像もしていなかった新鮮な感覚だった。審査委員それぞれが抱いている、広告業界や制作者に向けた切実なメッセージや個々の正義が投票・議論に宿っていて、作品の選択の先にある次の時代のCMの姿を願っていたように思う。審査をする前はコロナ禍の影響が如実に出るのではと考えていたが、多田審査委員長の言葉の通り「粛々と」ACCフィルム部門として世の中に今送り出すべき作品を見つめるよう心がけていた。
数字でCMをつくることが多くなった今に、右脳というより体のすべてを使ってつくり上げた迫力が宿った作品はやっぱり強く、人が人に届けるためにつくるCMの当たり前の尊さを再認識させてくれた審査会に感謝しています。 貴島 彩理 Sari Kijima
貴島 彩理 Sari Kijima- テレビ朝日
コンテンツ編成局 ストーリー制作部 プロデューサー
CMをこんなに沢山見るのは人生初でした。審査をしているはずがいつのまにか、キティちゃんの頑張りに涙したり、におわせに「やられたー!」とひっくり返ったり、洗濯を愛したくなったり、ジョーンズさんに励まされたり。映像の向こうからエールを送るような作品が多く、審査する側が元気を頂いたように思います。ということは、ここに集まったCMたちは、そんな風に日本のどこかで誰かを笑顔にし、勇気付けているのだとも思いました。
審査会はどこまでも熱く正直で、それでいて誇りに溢れていて、「CMとはこれでよいのか」と姿勢を問いただすような議論も何度もあり、自分も頑張ろうと刺激を頂きました。
貴重な経験をありがとうございました。 篠原 誠 Makoto Shinohara
篠原 誠 Makoto Shinohara- 篠原誠事務所
クリエーティブ・ディレクター
「なんであれがゴールド?」って憤ったり、憧れてきたACCだから、自分の1票に重みを感じた。多田さんは自分の基準で審査してほしいと、明快な審査基準を提示してくれた。「いい広告」とは何か、自分に問いながら1次審査。どんな長尺もしっかりみて採点した。全体を見た後で、また審査し直す。1日おいてもう一度。自分の中で3回審査した。次にファイナリストの2次審査。繰り返し見て自分の基準に照らし合わせる。最後に審査委員の意見を出し合っての審査。人の意見を聞いてまた見直す。丁寧に、でも自分の基準で。誰もが納得いく結果なんてきっとない。でも審査委員一人一人の基準と情熱で、フェアな審査が行われたことには100%納得いっている。
 高崎 卓馬 Takuma Takasaki
高崎 卓馬 Takuma Takasaki- 電通
エグゼクティブ・プロフェッショナル/クリエイティブ・ディレクター
今年の審査は面白かった。ひとつはすべてがオンラインだったため、かえって均等に発言の機会が生まれて、他の審査委員の方々の価値観や吸収の仕方をずいぶん激しく浴びたこと。もうひとつは自分より若い世代のかたまりを感じたこと。面白くもあり、他人の基準が体のなかに入り込んでくるのは微妙に辛くもある。実際、たくさんの言葉を浴びてそれがまだ体の底のほうに沈殿している。受賞作を見るとその幅とそれぞれの質の高さにあらためて納得をする。Netflixの確信犯的な仕事や、カネボウの感性を直撃する仕事など、とくに新しい世代の仕事に刺激をうけた。他にも自分がタブーだと思って避けていたことを軽やかにアイデアに昇華しているものを見ると焦りもする。まあ、とにかくいい経験だった。
 田辺 俊彦 Toshihiko Tanabe
田辺 俊彦 Toshihiko Tanabe- 電通
エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター
ACCの審査会は僕が思っていた伏魔殿のような
場所ではなかった。(よかった。。)
「いいフィルムとは何か」。
それぞれの審査員に異なる信念があった。
宗教論争みたいな議論もあったけど
全員が互いの意見を注意深く聞きつつ
それでもやはり流されずに主張を続けていた。
僕は時々流された。怖いけど恐ろしくフェアな場所だった。
マーケティングの手法は複合的になっている。
もはやフィルムは、そのシステムの歯車の一つでしかないという
意見はある意味まっとうに聞こえる。
でも本当にそうだろうか?
作り手が自らフィルムの可能性を矮小化して
あるフレームワークの中で縮こまっていないか?
それぞれの作り手の信念と執念が宿った今年の受賞作からは
そう問われているように感じた。 東畑 幸多 Kota Tohata
東畑 幸多 Kota Tohata- 電通
エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター/CMプランナー
「2020年を代表するCMは、どれだ?」
コロナ前とコロナ後が、混在する審査だからこそ、グランプリ投票は難しかった。「世の中が大変だからこそ、広告にやれることがあるのでは」「いや、世の中が大変だからこそ、広告は日常を継続する意味がある」。審査委員一人一人の価値観と美意識がぶつかり合い、自分の判断基準も、いい意味でグラグラと揺れた。「リザルトは関係ない。作り手としていいと思うものを選ぼう」という多田さんの審査方針が、フィルム部門の存在意義を明確にしたと思う。フィルム部門に、応募ビデオはない。その背景も、結果も、分からない。だからこそ、そのCMが「来るか、来ないか」広告表現に対して、最も高い純度で対話し、評価するカテゴリーになったのではないか。 浜崎 慎治 Shinji Hamasaki
浜崎 慎治 Shinji Hamasaki- ディレクター
今回初めてのACCフイルム審査委員。2日間行われたリモート審査会のうち初日に参加ができずそこだけ凄く悔やまれます(本当にすいません!)。事前審査を済ませおおよその予想はできていたものの、ゴールドからブロンズまでの賞についてはかなり僅差の戦い。ほんのワンタッチで票は動く。だから結果としてブロンズ作品もゴールドのチャンスは凄くあったわけだし、逆にゴールド作品もブロンズへの可能性は凄くあった。CMディレクター目線で見るとグランプリを争ったカネボウのI HOPEの演出力は群を抜いていた。そして、なんといっても審査委員長多田琢さんの指揮官としての采配が素晴らしかった。
 福里 真一 Shinichi Fukusato
福里 真一 Shinichi Fukusato- ワンスカイ
クリエイティブディレクター/CMプランナー/コピーライター
クリエイティブディレクターでは篠原誠氏、演出家では佐藤渉氏の時代が、ここ数年続いている感じで、篠原氏のトヨタイムズ、アタックZERO、佐藤氏の日清ラ王、この3つのどれがグランプリでもおかしくないな、と私は思いましたが、そうはならず、まあ、それらとは違うものを選びたい、というほかの審査委員のみなさんの気持ちもわかります。コロナに対応した、ポカリスエット、BOSS、サンリオピューロランド、サントリー話そうなどには、推す声もあったものの、強く反対する声もあり、それらもグランプリにはいたりませんでしたね。なかなかみなさん、ご意見が厳しいです…。というか、私、自分の意見と近いなと思えた審査委員が、テレビ朝日の貴島さんぐらいで、いかに自分が広告界で孤立しているか、あらためて思い知りましたね。前から薄々勘づいてはいましたけど。印象的だったのは、多田審査委員長が審査を通してなんだか疲れ果てていたこと。多田さん、大丈夫でしたか。おつかれさまでした。
 福部 明浩 Akihiro Fukube
福部 明浩 Akihiro Fukube- catch
クリエイティブディレクター/コピーライター
正直に言えば、審査に入るまでNetflixがグランプリになるとは想像していませんでした。
「人間まるだし」のコピーは抜群に素晴らしいけど、映像の賞であるACCではシルバーくらいかなと想像していました。
でも議論を重ねていくうちに、これだ!これしかない!
これこそグランプリだー!!となる自分がいました。
とても不思議な経験でした。(単に流されやすいだけ?)
そもそも広告について議論するなんて通常の視聴者からしたら、あり得ない訳だから、随分変わったことをしているのは確かです。
ただ、そこには審査員総意のメッセージがあります。
それは一言で言えば、「収まらないもの、創ろうぜ!」です。
CMの事前調査が当たり前のこの時代に、それでも先人達の金字塔を超えていこうとする気持ちは、やはり持ち続けていたいなと思うのです。
時代が違うからさ〜と言い訳するのは簡単だけど、というか、ほぼ毎日言い訳ばかりしてるけど、まあ、心意気としてはそんな風に思うわけです。
話は全然変わりますが、今の現役水泳選手たちって、昔、水泳界を席巻した高速水着を着ることを禁止されてるらしいですね。
記録が出過ぎるって理由で。でも、そんな中でもあの時代に作られた驚異的な世界記録を超えていく選手がいる。
そこに、とても勇気をもらうのです。そう、つまり、「僕たちは、進化している。」
そんな希望を微かに感じるから、日々、文句を垂れ流しながらも、前に進んでいかなきゃなと思うわけです。
人間まるだしで。 細川 美和子 Miwako Hosokawa
細川 美和子 Miwako Hosokawa- 電通
CREATIVE DIRECTOR/COPY WRITER
今こそ、きれいごとじゃない企業やブランドの本音や本気が知りたい。客観的に審査する側にまわって、あらためて気づきました。でも、企業やブランドの本音ってなんだ?それは実は「公式」印のついたものじゃない。関わる人たちのパーソナルな情熱だったり、嘘のない行動そのものだったりする。広告側が押しつけがちな幻想や枠にはめた結末から、どう自由になれるか。当たり前を疑って作っていけるのか。そして何より、伝えたいことをむきだしではなく、あきらめずに表現に変えていけるのか。そこに向き合って、この大変な一年もチャレンジを続けてきた作り手さんが確かにいることに励まされました。ありがとうございました。
 森本 千絵 Chie Morimoto
森本 千絵 Chie Morimoto- goen°
主宰/コミュニケーションディレクター・アートディレクター - 武蔵野美術大学客員教授
今年はオンライン審査だったにも関わらず、どんな審査よりも濃密な時間でした。審査委員それぞれが本音で語り合い、受賞作が決まるのに長い道のりでした。
とくに印象的だったことは、コロナ禍だからこそ、今の事態を反映し向き合って制作されたCMを評価したいという意見と、こんな状況だからこそ純粋に面白いCMを評価すべきだという意見が攻めぎあい続けたことです。また出品されているCMの半数は、こんな状況になるとは思ってもいない時期に制作されたものです。だからこそ審査をしていてとても難しかったです。CMは、いちばん世の中に影響する媒体なんだとあらためて感じました。まさに、今も状況に応じて新たなCMが次々に制作されていることと思います。どんなときであっても、商品を信じて出会えてよかったなと思える作品が増えることを願っています。 山崎 隆明 Takaaki Yamazaki
山崎 隆明 Takaaki Yamazaki- Watson-Crick
クリエーティブディレクター・CMプランナー
ACC審査の特徴と言えば、議論だ。
今年度も広告観も好みも異なる、いろんな尺度を持った審査委員の議論は白熱した。
特にAカテゴリーのグランプリ。
圧倒的な1等賞が不在だったこともあり、多数決だけに頼らず、時に1本のC Mを深掘りして、いろんな意見を戦わせた。
終わって思うのは、ACCの審査はフェアだということ。
多田審査委員長の冷静かつ本質を逃さないディレクションも圧巻だった。
それにしても最近、プランナーが過去のルールを基に張り切って作ったCMが古臭く感じてしまう。
時代とずれず、時代に媚びない。
そんな広告を制作者として作りたいし、視聴者としてもみたい。
審査委員が責任を持って選んだ今年の受賞作、皆さんにはどのように映るのか。 山田 智和 Tomokazu Yamada
山田 智和 Tomokazu Yamada- Caviar
映像作家/映画監督
- TUGBOAT
-
ラジオ&オーディオ広告部門 審査委員長
 井村 光明 Mitsuaki Imura
井村 光明 Mitsuaki Imura- 博報堂
第三クリエイティブ局 クリエイティブディレクター
音の聞こえ方を工夫した作品が上位に並びました。その中でも「ロボット掃除機ルーロ」は、「一度聴いただけなのに、ずっと頭から離れない」(審査委員・徳井さん)と、ずば抜けた印象で決戦投票を待たずのグランプリ。受賞作を見るとラジオCMらしい王道表現の年だったように感じられるかもしれません。
しかし、審査全体はラジオ&オーディオ広告部門に大きな変化を予感させるものでした。
昨年始まったBカテゴリーから初のゴールド受賞作となったパナソニック「Voice of Home」は、音を使う場所やタイミングに注目した作品。ややアウトプットをイメージしづらいBカテゴリー(音声を活用した企業コミュニケーション)でしたが、この作品は明快に考える指針を示し、今後Bカテに多くの作品が出てくることを期待させる好例となったのではないでしょうか。
また、ファイナリスト以上53作品のうち、実に3分の1がアンダー29の作品となりました。
ACC7部門の中でラジオ&オーディオ広告部門の魅力は、自由に作家性を発揮・実現できることではないかと考えています。「なんか面白いことができそうだ、自分もラジオに参加してみたい」、そう感じてもらえるメッセージを発信していきたい。
その点で今年のサプライズはなんといってもブロンズ入賞の「新日邦」でしょう。毎年フィルム部門で大暴れしているあの「コンコルド」がラジオにやって来た! 審査委員にはあの鶴光さんもやって来た! そしてたくさんの広告主やクリエイターがラジオに集まってくる。そんな力強い流れを感じた審査会でした。ラジオ&オーディオ広告部門 審査委員
 加藤 慶 Kei Kato
加藤 慶 Kei Kato- 文化放送
編成局編成部次長
審査委員としてお招き頂き、改めて御礼申し上げます。
各クリエイター様の知恵と情熱が込められた作品に触れさせて頂き元気を頂くとともに、楽しい時間を過ごさせて頂きました。
「2020 60th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS ラジオ&オーディオ広告部門」の審査会に参加させてもらうことで、「そもそもCMとは〝嫌われる“前提であるもの」ということを再認識しました。
〝嫌われる”ゆえに、いかに“振り向いてもらうか”、ひいては、”いかに好きになってもらうか“、その為の工夫を凝らしてゆく作業こそが、民放の”当たり前”でなければならいことを多くの作品を通じて改めて強く感じさせて頂く場でした。
ご応募頂いた多くの方が頭を悩ませながら凝らされた工夫に感服した時間でした。 澤本 嘉光 Yoshimitsu Sawamoto
澤本 嘉光 Yoshimitsu Sawamoto- 電通
シニア・プライム・エグゼクティブ・プロフェッショナル/エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター
今年のACCラジオ&オーディオ広告部門は、最終的に賞に選ばれたものが「音を使って遊ぶ」というラジオCMの楽しみ方の原点回帰をしているものが多い。
逆に、コピーがキレてる、というような、原稿の言葉選びのチカラで受賞した、というものが少なかったと思っている。
こういう年があっても、ラジオCMというもの自体の魅力の再確認にはいい気がする。
音の作り出す創造力の世界は、絵がない分だけ広大で果てしない。
一方、会話のやりとりだけで吹き出してしまうようなものも、来年はぜひ上位の作品として聞きたいな、と期待している。
総体の中の受賞本数のパーセンテージが決まっているとは知りつつ、もっと多くに賞をあげて多種多様な形態のCMが褒められるといいなあ、と個人的には感じた。 嶋 浩一郎 Koichiro Shima
嶋 浩一郎 Koichiro Shima- 博報堂 執行役員
- 博報堂ケトル クリエイティブディレクター・編集者
「AIというものは学習して進化する」。ものの本やニュースにはそう書いてある。しかし、そのことを感覚的に納得するのはむずかしい。グランプリに輝いたパナソニックロボット掃除機ルーロのCMはこの理解しづらい概念を直感的に体感させてくれた。これはなかなかできることではない。「ビフォアー、アフター」はCMの一つの手口だけれども、ラジオCMを聞く前の自分と聞いたあとの自分が明確に変化していることを体感できる仕掛けを考えたのは新境地。Bカテゴリー、パナソニックの社内放送で働き方改革を進めるという野望が素敵です。音声は生活のなかに忍び込むのが得意。Bカテゴリーはアイデア次第でいろいろ挑戦できる領域だと思っています。
 笑福亭 鶴光 Shofukutei Tsuruko
笑福亭 鶴光 Shofukutei Tsuruko- 松竹芸能
- 落語家
いやーほんとにねー、人を審査する、物を審査するちゅうのは難しさを始めて知りましたね。
わずか20秒30秒の中に、あれだけいろんな人が考えて、知恵を絞って一つの作品をつくりあげるというのは、ものすごいことであって、それを審査させてもらうというのは非常におこがましいことですけど、ものすごい勉強になりました。
せやから、これからラジオCMは真剣に聞きたいと思います。 徳井 青空 Sora Tokui
徳井 青空 Sora Tokui- エイベックス・ピクチャーズ
声優・漫画家
今回は大変貴重な経験をさせていただき本当にありがとうございました。ラジオは聴くのも出演するのも大好きなので、初めての審査委員に緊張しましたがとても楽しかったです。また、普段から声優として言葉や音の大切さを強く感じていましたが、改めて音だけで伝える面白さや難しさに気づくことが出来ました。掛け合いが面白いもの、聴き心地の良いもの、ハッと胸に響くコピー、耳に残る音楽…。どの作品もそれぞれ魅力的でなかなか迷ってしまいましたが、せっかくなので自分なりの評価をと思いリスナー目線で直感的に気になる作品を推させていただきました。U29のクリエイターさんの作品も多く、私も創作意欲が湧いてきました!!
 西田 善太 Zenta Nishida
西田 善太 Zenta Nishida- マガジンハウス
BRUTUS編集長
大日本除虫菊「ゴキブリムエンダー」シリーズ/驚異的なラジオCMです。コンマ何秒ごとの複雑な演出、セリフ、音楽の転調、テイストの昭和な仕上げ、商品説明すべてが完璧に構成されていて、個人的意見ですが、映像1フレームごとに加工していくiPhone12Proに匹敵するほどの、僕のグランプリです。
若い作り手はまず、いい聞き手になってください。聞く人は話す人になります。そして、話す人は書く人でもあります。これは20代の頃、眞木準さんに言われた言葉です。過去にさかのぼって、たくさんのラジオCMを聴いてほしい。ラジオは時間モデル、早送りもぱら見もできないから、聴いた時間が全部、身につきます。今回、広告制作の若手、20代の応募が増えたのがうれしい傾向です。20代向けの「U-29」賞の枠が発展的解消するほどに! 普通のコピーはいくつになっても書けるから、おもしろいコピーこそ若いうちに書き慣れておくのが得策です。そのいちばん簡単なデビューの場所が、ラジオCM。今のうちです。あと、ラジオもたくさん聴いてね。 橋本 吉史 Yoshifumi Hashimoto
橋本 吉史 Yoshifumi Hashimoto- TBSラジオ
プロデューサー
2020年は音声コンテンツにとって実は大きなスタートの年ともいえる。海外でのブームを受け日本においても「Podcast元年」と呼ばれ、SNSや動画配信に続き、誰もが音声コンテンツを発信できる時代であることが周知されてきた。スマホで録音編集配信まで手軽にできることもあり、音声で何かを表現していく潮流は益々大きくなっていくと思われる。つまりラジオは古参メディアでありながらまた新しいメディアのように認知されているのである。そんな中、もっともアイディアと手間が凝縮されたショート音声コンテンツがラジオCMである。関わる人数が少ない分だけクリエイターの発想力をストレートに形にしやすいため、毎年あっと驚く手法の作品を出会えることが審査の醍醐味。コロナ禍においてもその表現の多様性は変わらないどころか、その特殊な状況をもクリエイティブに活かしてくるあたり、音声コンテンツの未来は明るいと思ってしまうのであった。
 古川 雅之 Masayuki Furukawa
古川 雅之 Masayuki Furukawa- 電通関西支社
グループ・クリエーティブ・ディレクター/CMプランナー/コピーライター
初めての審査会。票が割れに割れた。ぼくが票を投じたものは、ほぼほぼ選外に。ここで文字数の限り。エフエム栃木「切り株」、ラストのコピーが秀逸。カロリーメイト「受験の不安」、リアリティとリズム。出光興産「潤滑油」、笑った。パイロット「なまえペン」、下品の品。味の素「矛盾の歌」、よく見つけている。AC「犯罪者のセリフ」、どきっとさせる。出雲葬祭のシリーズ、指宿白水館「ホントのところ」、つちや「文具って青春アイテム」。受賞作は、割と「オーソドックス」で「わかりやすい」「音ネタ」が強かった。そこに、私憤剥き出しの「もやる人」と、わかりやすいの真逆「コンコルド」が食い込んだ。わかりやすい音ネタは、ラジオCMの原点回帰とも言えるが、それには既視感がある。
 三井 明子 Akiko Mitsui
三井 明子 Akiko Mitsui- ADKクリエイティブ・ワン
コピーライター/クリエイティブディレクター
審査開始から発表までタイムリミットは数時間!!!なにかに追われるとどきどきそわそわしてしまうわたしには、緊張がはしる審査会でした。一方で、井村審査委員長のもとでの審査は本当にたのしく、ずっとこの審査がつづけばいいのに…と、こころから感じていました。たのしい上にやさしい心づかいで、発表にも間に合わせてくださった井村さん、ありがとうございました!受賞作では、グランプリとゴールドのパナソニック作品が、「AI」「働きかた」と、いずれも時代性をとらえ、しかも、どちらがグランプリになってもおかしくないクオリティ。そのふたつを同じ制作者が手がけられていることに、嫉妬を超えた羨望と敬意を抱きました。畠山さん、おめでとうございます!
- 博報堂
-
マーケティング・エフェクティブネス部門
審査委員長 鈴木 あき子 Akiko Suzuki
鈴木 あき子 Akiko Suzuki- サントリースピリッツ
執行役員 RTD・LS事業部長
部門名に「エフェクティブネス」をうたっていることがこの部門の一つの特徴だと思います。多種多様なキャンペーンの「成果」に優劣をつけるのは本当に難しく、毎年審査会で激論となるところです。だから、どんな目的や課題認識に対しての成果なのかをセットで論じます。また、それを実現するためのコアアイディアの新しさも大きな評価ポイントです。
当日の公開プレゼンテーションに進んだメダリストの11組は、その点は全てクリアしているチームです。プレゼンテーションではさらに、どれだけ本気で取り組んでいるのかが全てのチームから伝わってきました。今年はコロナをきっかけにオンライン公開となりましたが、むしろこの方法を来年以降も続けて、日本全国のたくさんのマーケッターに視聴してほしいと思います。必ず勉強になるところがあるはずです。
各審査委員は今年も活発に様々な視点を提示してくれました。議論の末、今回はマーケティングエフェクティブネスの王道、全国の企業のマーケッターを勇気づける作品をグランプリに選ぶこととなりました。ロングセラーブランドの売上V字回復は本当に難しい仕事ですが、新しい価値軸を発見すること、そして製品を真ん中に置いて全ての施策を強力な一つの線でつなぐことで現状をひっくり返し、マーケティングの底力を見せてくれました。マーケティング・エフェクティブネス部門
審査委員 上野 隆信 Ueno Takanobu
上野 隆信 Ueno Takanobu- 大塚製薬
ニュートラシューティカルズ事業部 宣伝部 課長
最終審査は、2次審査を通過した11チームによる公開プレゼン形式。公開プレゼンも3回目でやっと慣れてきたと思ったら、今年はAR空間でのWEB配信。初めての事に審査する側の私はドキドキでした。しかしプレゼンをする方は連係プレーまで見られ、皆さん手慣れた印象です。資料だけでは伝わらなかった部分まで見え、例年以上に甲乙つけ難い施策ばかりでした。グランプリは、審査委員全員納得の今年を代表する施策です。製品を真ん中に置きつつ、コモディティー化した市場をプロダクトとクリエイティブ、コミュニケーションまで一気通貫しトップブランドへ。同じような課題に苦慮されている多くの人の解決のヒントとなり道標となる施策だと思います。
 大澤 あつみ Atsumi Osawa
大澤 あつみ Atsumi Osawa- トヨタ自動車
国内販売部 主任
たくさんの素晴らしい作品、ファイナリストの公開プレゼンを見て、各社様のチャレンジングな取組みにとても刺激を受けました。
審査会では「どこをマーケティングして、何がエフェクティブネスかが明確であること」「ブランドパーパスが明確であること」などのキーワードが印象的でした。
審査委員の方々も様々な立場からのご意見があり、評価の軸が複数ある中で納得のいくまで議論をし尽くしせたことも、大変勉強になりました。
グランプリを決めるのは非常に難しかったですが、とても楽しかったです。
貴重な機会をありがとうございました。 太田 郁子 Ikuko Ota
太田 郁子 Ikuko Ota- 博報堂ケトル
代表取締役社長 共同CEO
PRディレクター/ストラテジックプランニングディレクター
今年の受賞作の顔ぶれは去年までとひと味違います。部門名により忠実に「マーケティングエフェクティブネス」を評価した結果だと考えています。2020年、日本経済が大きな経済的打撃を被る中、企業に求められる最大の社会貢献は、アイディアを研ぎ澄ませ、覚悟を持って難局に向き合い、利益的成果を出して経済を止めないことなのかもしれません。
また「継続」も今年を語るキーワードでした。継続に足る骨太な戦略はもちろん、継続にも「覚悟」が求められます。「覚悟」があるから仲間や賛同者が増える。不確実性の時代に、覚悟という確実性こそがマーケティングの推進力になりえるのでしょう。 奥野 圭亮 Keisuke Okuno
奥野 圭亮 Keisuke Okuno- 電通
- クリエーティブ・ディレクター
市場を動かす魔法なんてない。
そんな当たり前だけど、とても大切なことを教えてもらった今年の審査会でした。時として僕たちはマーケティングという言葉を魔法のように使ってしまっていないだろうか。「商品はこれです、あとはマーケティングで」的な。今年のグランプリは緑になった伊右衛門。ペットボトルのお茶は茶色が多いという発見から、味との両立にこだわったプロダクトを開発し、コミュニケーションまで一貫して「緑」にこだわった努力の積み重ねが、結果的に市場に大きなインパクトを生み出した。これはゴールドのリプトンや日興フロッギーにも通じる。「1%の発見と99%の努力」というマーケティングの基本に返ることができました。 佐々木 亜悠 Ayu Sasaki
佐々木 亜悠 Ayu Sasaki- 電通
- クリエーティブ・ディレクター
今年のME部門では、特にコロナ禍でのエフェクティブネスをどう捉えるか、ということが議論されました。コロナに負けずにモノを売ったことのすごさは?「無欲の成功」はマーケティングか?何年も継続してきた活動をどう評価するか?
広告の文脈では、いま世の中で起きていることに対してただちに反応することが良しとされることが多い。それはそれで大事なことだと思うのですが、一方でこうした非常時だからこそ、骨太な社会的使命を持っていることが垂直立ち上げにつながったり、中長期的な積み上げが成果に変わったりするケースが多くみられました。そうした「倒れない土台」や「価値に変わる継続」の凄みのようなものを感じた審査会でした。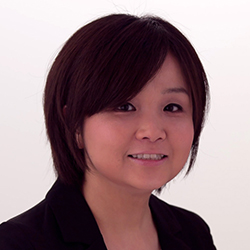 白井 明子 Akiko Shirai
白井 明子 Akiko Shirai- ローソン
- マーケティング戦略本部 部長
今年の審査会は、オンライン開催で審査委員がリアルで会うのは最後のプレゼンテーションの時が初めてでした。例年と違って2020年はコロナ禍だからこそ生まれた作品も多く、審査委員によって評価が分かれたのも印象的でした。
 高田 伸敏 Nobutoshi Takada
高田 伸敏 Nobutoshi Takada- 東急エージェンシー
クリエイティブ局局長
エグゼクティブクリエイティブディレクター
課題解決型のスタートアップが増えたり、昨日までパン屋さんだったのが明日からエコバイク売ります、みたいなビジネスアイデアも素敵だけど。そもそも、なぜそのブランドが生まれたのか、ブランドを長く愛してもらうためにどんなアイデアと努力で市場と戦ったのかを今年は評価したいと思いました。グランプリのサントリー「伊右衛門」は、緑茶市場という巨大マーケットの中で、大胆なアイデアで見事ナンバーワンに。淹れたての緑に着目し、その鮮やかな緑を体験してもらうために裸になってみせた。これだけ差別化しにくい市場で、今までやったことのないアイデアを実行することは相当な勇気がいることです。売れる=生活者に愛される。まさにエフェクティブネスなグランプリでした。
 辻 毅 Takeshi Tsuji
辻 毅 Takeshi Tsuji- ADKクリエイティブ・ワン
クリエイティブ本部 本部長
新型コロナ感染症拡大の影響で今年のME部門はどうなっちゃうんだろう?
という僕の心配は杞憂に終わりました。
ハイレベルな戦いに審査会も大盛り上がり。
コロナ禍でも下を向かずにマーケティングの力で世の中の課題を解決しようと奮闘する数多くの出品作の熱量に勇気をいただきました。
そんな熾烈な争いの中でも「緑の伊右衛門」は強かった!文句なしのグランプリ。
記録的な数字をたたき出した戦略に圧倒されました。
最終グランプリ審査は、リプトンとの一騎打ち。
まさかの「東西お茶対決」となりましたが、軍配は伊右衛門に!
これこそが、エフェクティブネスだよね!
と審査委員を唸らせるお手本のようなキャンペーン。
後味のさわやかな審査会となりました。 西田 裕美 Hiromi Nishida
西田 裕美 Hiromi Nishida- カゴメ
マーケティング本部 飲料企画部長
「覚悟」これが今年の審査のキーワードだったと思います。グランプリ受賞者の「崖っぷちでしたから」というコメントが印象的でした。今年はコロナ禍というこれまでにない環境下、多くの事業が予測困難な将来に立ち向かうことを余儀なくされています。マーケティングに正解はありませんが、課題に直面しても、チームの想いを一つにし、より良い未来に向けて知恵と努力を最大化し、細部に及ぶまで戦略を組み立て実行し、活動を進化させる、というサイクルが成功を導くということ、つまり基本プロセスに立ち戻り愚直に突き進むことの大切さを再認識致しました。受賞された皆様、本当におめでとうございます!
 松井 美樹 Miki Matsui
松井 美樹 Miki Matsui- 博報堂
クリエイティブ戦略局 局長
「オンラインだからこそ思い存分語れる」という初体験。6つの相対する方向からのクロスファイア。事業会社からvs広告会社から。マーケティングからvsクリエイティブから。アナログからvsデジタルから。男性からvs女性から。ACCで最も多様な審査委員たちだからこそ到達できた境地。毎年レベルアップしていくマーケティング・エフェクティブネスのプレにもっとたくさんのオーディエンスが来て欲しいと切に願う。グランプリと金は、まさにこれからのマーケティングの可能性を表現していて興味深い。「ちゃんと体感できる商品開発へ」「プロダクツから体験&サービスへ」「DXを味方につけた暮らしのトランスフォーメーションへ」
 簑部 敏彦 Toshihiko Minobe
簑部 敏彦 Toshihiko Minobe- 花王
作成部門 広告作成部 広告作成部長
新しさや突破力といった「点の強さ」と、持続可能で成果を重ねる「線のしなやかさ」。比べられないけれど、どちらの視点もポイントだと、議論の熱量が増すたび感じました。それはME部門が持つ、ブランドや社会の未来を照らす大きな役割も意味するのだと思います。
初めて参加させていただいたACC賞の審査は、オンラインもリアルも、想像以上に熱くて、悩ましくて、楽しくて、とても刺激的な時間。そしてマーケティングに関わる人たちにとって「明日の勇気をもらえるものを選ぼう」という、審査委員長をはじめ、審査委員のみなさんのこころざしに、僕自身が勇気づけられました。ありがとうございました。 宮園 香代子 Kayoko Miyazono
宮園 香代子 Kayoko Miyazono- ソフトバンク
東日本エリア営業本部 本部長
世の中がコロナで一変した今年ですが、ME部門の作品は厳しい市場環境を吹き飛ばすアイデアとクリエイティビティで、意欲的に市場を動かそうとする取組ばかりでした。
最終プレゼン審査の企業からは強い自信が感じられ、エフェクティブネスも明確でどれも魅力的。自分の優柔不断さに萎え、思考がぐるぐる回りながらも、審査委員間でのポジティブ議論が炸裂したおかげで、最後は納得感のある決定をできたと思います。とはいえ、まだ自分の中で答えの出ない「単発」か「継続」か。マーケティング活動はいつを頂点として評価されるのか。今年の代表を決めるというのは難しいですね。勉強になりました。
受賞された皆様、本当におめでとうございます。 - サントリースピリッツ
-
ブランデッド・コミュニケーション部門
審査委員長 菅野 薫 Kaoru Sugano
菅野 薫 Kaoru Sugano- 電通
エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター
ブランデッド・コミュニケーション部門3年目。コロナ禍で、応募数は少なくなるのではと予想していましたが、蓋を開けたら、全カテゴリーで過去最高の応募数。数だけでなく、質も過去最高といって良いのではないかというくらいレベルが高く、日本のクリエーティビティの勢いと底力を感じる年になりました。
それにこたえるように、リモート審査ではありますが、贈賞を検討したすべての作品について丁寧な議論を行い、議論後に再度投票しなおすという丁寧なプロセスで審査を行ったため、部門全体で計4日間、28時間半に渡っての審査となりました。
Aカテは、ここ数年応募数ものびず停滞していたような印象もあったのですが、今年は、これから我々のクリエーティビティがデジタルエクスペリエンスで貢献すべき数多くの方向性が提示された示唆のあるカテゴリーになりました。グランプリはまさにそのひとつ。粘り強く、効くプラットフォームがつくられました。
Bカテは、もっとも多くの作品数が応募され、もっとも幅が広く、もっとも質の高い仕事が多く応募されたカテゴリーになりました。ブランドのための仕事をしている我々の今をもっともあらわしているカテゴリーかもしれません。
グランプリは、社会的に動かした実績はいわずもがな、丁寧で誠実な仕事で、世の中を幸せにしてくれたプロジェクトです。
今年ほど、人間が、企業が、社会的な存在であることを実感した年はないかもしれません。
Cカテは、社会的な大きなテーマを顕在化させ、社会の中で合意にむけてコミュニケーションしていく、投げかけを世の中に広げていく技術のカテゴリーです。この時代に、我々の仕事は、どうあるべきかを考える大きな示唆をくれる審査になりました。ブランデッド・コミュニケーション部門
審査委員 石下 佳奈子 Kanako Ishioroshi
石下 佳奈子 Kanako Ishioroshi- 博報堂
- クリエイティブディレクター/コピーライター
審査委員のみなさん、褒め方がうまいんです。ぞれぞれの専門分野のプロが集まっているので、ありとあらゆる視点で褒めるんです。でもほら、褒める技って、コミュニケーションのヒントを見つける技でもありますよね。どのポイントが、人の心を動かしたのか。どのポイントによって、いちばん効果を出したのか。よく、デコンとかリコンとか言いますが、「ありとあらゆる手を使って褒めちぎってみる」ことを日頃の癖にすると、広告に限らず、いろんな事がうまくいく気がしてなりません。
 井上 佳那子 Kanako Inoue
井上 佳那子 Kanako Inoue- 博報堂
プランナー
ブランデッド・コミュニケーションの審査には、個性あふれる様々な審査委員が参加しています。それぞれの得意としていることも、美学も、背負っているものも違う。だからこそ、審査がすごく刺激的です。ある視点で見たら素晴らしい作品も、違う視点で見たらどうなのだろうと迷うこともある。たくさんの議論の結果が、受賞作品という形で発表されています。私たちは、これからの「広告」が、どうなっていって欲しいのかを示しています。いつでも、広告は、人の心をポジティブにしたり、物事を話し合うきっかけになったり、「世の中を進める」ことができるはずだから。そんな広告が今後も溢れることを願っています。
 イム ジョンホ Jeong-ho Im
イム ジョンホ Jeong-ho Im- mount
代表取締役/Art director
この審査会は、やはり、なんというか毎回、疲れます。今年はコロナ対策としてオンライン審査会をしたもので、より疲れました。どれひとつ妥協することなく、すべて議論し尽くし決めていくプロセスだからこそ、疲れます。終わった後は達成感と共に心地よい疲労感が訪れるとともに、この賞をとることって、とても難しくて名誉あることだなぁ、おめでたいなぁ、うらやましいなぁと思います。
受賞された、みなさま、心から、おめでとうございます。褒められるっていいですね、うらやましいです! 上西 祐理 Yuri Uenishi
上西 祐理 Yuri Uenishi- 電通
アートディレクター/グラフィックデザイナー
 大八木 翼 Tsubasa Oyagi
大八木 翼 Tsubasa Oyagi- SIX
エグゼクティブクリエイティブディレクター/パートナー
 尾上 永晃 Noriaki Onoe
尾上 永晃 Noriaki Onoe- 電通
プランナー
フルリモートの審査が増えて、なんとなく結果に偏りがあるように見える今年のアワード。
ACCの最終審査は十分すぎるほど距離をとってリアルで実施したことで感情がのり、バラエティ豊かな仕事が受賞したように思えます。
残ったものに共通していたのは「愛」かもしれません。
バラバラになりそうなときこそ、それを繋ぎ止めてくれる「愛」が大事なのか。
関係なく普遍的に大事なことなのか。いずれにせよ、愛される仕事をしていきたいと思いました。
突然ですが、こういうコメント欄はその人が本当に大事だと思っていることが多い傾向にあるので、もし競合で相手になったらそこを突くとおトクかもしれません。
と愛のあるんだかないんだかってコメントで〆させて頂きます。 栗林 和明 Kuribayashi Kazuaki
栗林 和明 Kuribayashi Kazuaki- CHOCOLATE
- 取締役/Chief Content Officer
 小杉 幸一 Koichi Kosugi
小杉 幸一 Koichi Kosugi- onehappy
クリエイティブディレクター/アートディレクター
ブランドのためになっているか。
ひいては、世の中のためになるブランドになっているか、なっていくか。
そう言った点でこのブランデッド・コミュニケーション部門は、企業や事業、商品の目的のためというシンプルなビジョンの元、そのための手法の多様性や必然性、可能性から未来を見据えて、世の中に翻訳することの部門なんだと思います。
非常に領域の広い、また一人一人の信じる憲法が違う審査委員が各々翻訳し、意見をぶつけ合うプロセスから受賞されたお仕事は、まるでさまざまな解像度の濾過装置を通り抜けた、濁りなき純粋かつ感動に値する広告業界に勇気を与えてくれるものでした。
関係者のみなさま、誘っていただいた菅野さんありがとうございました。
そして受賞者のみなさま、心からおめでとうございます。 小布施 典孝 Noritaka Kobuse
小布施 典孝 Noritaka Kobuse- 電通
Future Creative Center センター長/エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター
クリエーティビティには世界を変える力がある。今回はじめてACCの審査委員をやらせて頂き、あらためてその想いを強く持つことが出来ました。こんな本質課題の導き方があるんだ。こんなアプローチでの解決法があるんだ。こんなリザルトまで導けるんだ。いくつもの事例を通して、たくさんの驚きと勇気を頂くことが出来ました。いま多くの企業で搭載されているロジカルシンキングという発想法がコモディティ化してきている状況にあるからこそ、このクリエーティブシンキングというものに改めて可能性を感じた、そんな審査会でした。素敵な機会を頂きまして本当にどうもありがとうございました。
 佐々木 康晴 Yasuharu Sasaki
佐々木 康晴 Yasuharu Sasaki- 電通
- デジタル・クリエーティブ・センター長/エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター
その他なんでも係のようにして始まったブランデッド・コミュニケーション部門は、ここにきてその本領を発揮し、プロダクト&サービスからデジタルトランスフォーメーションの仕掛け、Web動画に、社会を変える活動・取り組みなど、面白い応募がいろいろ揃ってきました。その多様性が何より素晴らしい。最終的にはそれらを「賞」というひとつの順列の上に置かなければならないけれども、今後のクリエイティブの発展のためには、ビジョンが良いもの、アイデアが良いもの、実現手法が良いもの、リザルトが良いもの、それぞれのいちばん良いところを褒め、それぞれの良さがみんなに伝わる部門でなくてはならないと思っています。メダルの色よりも、入賞しているものすべてに、それぞれ違う素敵な価値があると感じています。
 嶋 浩一郎 Koichiro Shima
嶋 浩一郎 Koichiro Shima- 博報堂 執行役員
- 博報堂ケトル クリエイティブディレクター・編集者
SDGs経営の浸透や、老朽化する団地の問題など高度な社会課題を「その手があったか」というクリエイティブな手口で解決するレベルの高いPR施策がゴールドに選ばれた。クリエイティビティのインストールはPR業界の課題であり、まさにACCらしい視点での選考ができたと思う。BC部門にパブリック・リレーションズの仕事を評価するカテゴリができて3年経つが、たったこの3年の間に日本のPRインダストリーのアウトプットが進化したことが伺える。社会における合意形成というハードルの高い仕事が多数見受けられ、刺激を受けた。
 嶋野 裕介 Yusuke Shimano
嶋野 裕介 Yusuke Shimano- 電通 CDC
クリエーティブ・ディレクター/PRディレクター
PR部門のわたしの審査基準は、まずは①Earnedであるかどうか。ついで、②Branded であり、③Effective & Efficiency かどうか。最後に、業界を前に進める意義として④New であるものは別途加点しました。ACCにPR部門がある意味はPRの専門家だけではなく「コミュニケーションのプロたちで決める」ことにあると思います。そのため海外PR賞を受賞しまくっている仕事があっけなく予選落ちしたり、他のPRの賞だと絶対拾えないものがゴールドになったりすることも(グランプリを決める議論はとても楽しかったです)。この結果は、PR会社や代理店の若手PRパーソンにこそ見てもらいたいです。こんなに自由なPRを認めてくれる賞があると、もっとみんなのびのびと仕事できるんじゃないかなぁ。
 清水 幹太 Qanta Shimizu
清水 幹太 Qanta Shimizu- BASSDRUM
テクニカルディレクター
2020年は、デジタル領域における「クリエイティブ」の概念が明確に変化した年でした。生活をより楽しくする、悪い言い方をすれば「贅沢品」だったデジタルクリエイティブが、厳しい情勢の中で社会にとって必要不可欠な、仕組みづくりを担う存在になりました。
驚きと新しさを競う場であったACCのようなアワードでの評価軸も同時に大きく変わろうとしている時代だと思います。審査会では、世相の厳しさに反して次代に向けた大きな変化が議論の中心になったように思います。
ソーシャルメディアを中心とした施策がある種の焼き畑状態で停滞していた昨今、ようやくトンネルの出口が見えてきた。そんな手応えを感じさせてくれる審査会でした。 東畑 幸多 Kota Tohata
東畑 幸多 Kota Tohata- 電通
- エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター/CMプランナー
BC部門は、超激戦区だった。そして、カテゴリーの壁は、完全に崩壊した。
デジタル、PR、プロモーション、すべての点において、高い次元で融合しないと、もうBC部門では通用しない時代に突入した。全体のレベルが高く、ファイナリストに残った仕事は、すべて賞賛に値すると思う。たった2年前に、BC部門は「その他部門」であり、辺境の異種格闘技。というタイトルで、審査委員座談会をしていたが、もうBC部門は、新しい可能性を発見する役割から、もしかしたら広告クリエイティブのど真ん中に移動してきたのかもしれない。「辺境」と「ど真ん中」、どっちが幸せかは分からないけど、、、そんなことを感じた審査会でした。 橋田 和明 Kazuaki Hashida
橋田 和明 Kazuaki Hashida- HASHI
クリエイティブディレクター
PRというものは「世の中を動かすドキュメンタリー」だと感じた。ゴールドをとった3作品はもちろん、池江さんのThis is me.や#NoBagForMeなど、どの仕事にも、単なるFACT(事実)をこえたTRUTH(真実)が発見されていた。それをメディアや世の中が巻き込まれるように、綿密に計画され、ドキュメンタリーにしたてあげられている。広告のような、フィクションのような派手さはない。けれども、クリエイターの意志と情熱がたっぷりと入ったドキュメンタリーには、非常に心を動かされるものがあった。今回の応募された仕事にはまだ継続しているものも多くある。その続きにも期待したい。
 畑中 翔太 Shota Hatanaka
畑中 翔太 Shota Hatanaka- 博報堂ケトル
クリエイティブディレクター/プロデューサー
今年はコロナ禍で一時、日本の経済活動がストップしていたにも関わらず、審査をしたBC部門でも例年以上の応募が集まり、何より作品のレベルが高かったACC賞審査。コロナ禍における施策とそうでないものが混在する中で、今年のACCが何を「正」としていくか?が問われていた年だったと思います。審査を終えてみて、2020年のその“混在さ”が逆に、ときに「物を動かすマーケティング」として、またときに「コロナ禍で不安になる人々の心に寄り添うソーシャルキャンペーン」として、「広告」というものの持つ力を改めて証明してくれた、そんなACCだった気がします。応募していただいた皆さま、ありがとうございました。
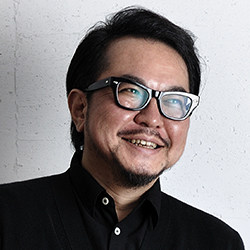 原野 守弘 Morihiro Harano
原野 守弘 Morihiro Harano- もり
クリエイティブディレクター
批評なき業界は廃れる。映画にせよ、ミュージカルにせよ、批評家と制作者の間に緊張感があってこそ、よい作品が生まれる。海外には広告を批評するジャーナリズムが存在するが、日本はない。SNS全盛の昨今、広告やPRの業界も、言ったもの勝ち、盛ったもの勝ち、というのが時代の風潮だが、批評なき業界は廃れるという言葉が、現実化しつつある。ACCの菅野さんカテゴリーは、審査過程を議事録に残して公開するという試みを続けている。広告賞は応募された作品しか議論できないし、審査委員もプロの批評家ではないが、これが日本の広告批評の最後の砦だと思う。作品の批評として読むのもいいし、審査委員の行動や発言を批評の対象にするのもいいだろう。すべての部門で採用すべきルールだと思う。
 細川 美和子 Miwako Hosokawa
細川 美和子 Miwako Hosokawa- 電通
クリエーティブディレクター/コピーライター
広告ってここまでやれるんだな。作り手が繰り出してくる想像を超える角度のチャレンジにチカラをもらったり、自分が情けなくなったり、感情が忙しい審査会でした。中でもうれしかったのは、長くブランドに寄り添って育てていく覚悟がある広告が、増えてきたこと。ブランドの社会にとっての存在意義と向き合って、関わるすべての人にやりがいのあるビジョンに、再定義している企業が多くなっていること。広告が一方的な発信に終わらずに、コミュニケーションであろうとし続ける意志をBC部門で特に強く感じました。そして当たり前の枠組みを疑い続け、作り続ける最前線の姿勢と視点を学ばせてもらいました。審査が終わった日はクタクタでした。
 三浦 崇宏 Takahiro Miura
三浦 崇宏 Takahiro Miura- The Breakthrough Company GO
代表取締役/PR/CreativeDirector
ACC審査会、それは、日本最高峰の知を共有する議論であり、高度に政治的な会議であり、広告業界に対するクリエイティブディレクションであり、個人個人のメンツと喋りの技術をぶつけ合うフリースタイルバトルであり、愛のあるディスり合いであり、クリエイティブという技術体系の進化の検証の場であり、知性とユーモアを競い合う大喜利であり、大人たちが青臭い信念をぶつけ合う真剣30代ー50代しゃべり場であり、この仕事への愛をぶつけ合う告白の場でもある。
こんな知的なエンタメはない。
全部まるっと生配信すればいいのに。
来年に向けてぜひご検討ください。 八木 義博 Yoshihiro Yagi
八木 義博 Yoshihiro Yagi- 電通 CDC
クリエーティブディレクター/アートディレクター
ブランデッド・コミュニケーションの名前の通り、ブランドの発言に説得力や必然性があるか、相応しいアイデアやクラフトがあるか、そのブランドの人格を感じたい。今年はいかに誠実であるか。が自分の中でキーワードとなりました。日興フロッギーの仕事は証券会社としてのCSRを本質的に捉え、日本人のウィークポイントとされている投資の分野に鮮やかに切り込んでいます。「投資の本質は成長」として、人々の投資する気持ちを良い方向に導こうとする構図は、ちょっといい未来を見せてくれます。ブランドの描く未来のビジョンに人や社会が共鳴して歩んでいく。そんな仕事にしたい、頑張らねば、役に立ちたい。そう思わせてくれる審査会でした。
 保持 壮太郎 Sotaro Yasumochi
保持 壮太郎 Sotaro Yasumochi- 電通 CDC Dentsu Lab Tokyo
コピーライター/プランナー
コロナみたいな出来事に直面すると、つくづく僕らの仕事って無力だなと思う。でも、よく考えてみると、僕らはいつだって無力じゃないかとも思う。天候とか自然現象に常に左右される。政治とか経済の動きにも振り回される。人間関係ひとつで全てがひっくり返ったりする。そのたびに、ああ無力だなと思う。でも、僕らの仕事に矜持があるとすれば、それはあきらめの悪さじゃないだろうか。どれだけ追い込まれても、最後までアイデアでどうにかしようとしてしまう。その往生際の悪さこそ、僕らの真骨頂。今年も審査を通じて、最後まで考えることをやめずに粘りつづけた人たちの痕跡を随所に感じることができた。無力さを嘆いている場合じゃない。自分ももっとやらなきゃ。
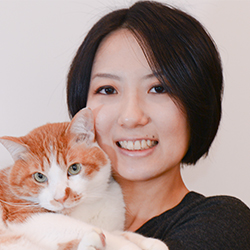 米澤 香子 Kyoko Yonezawa
米澤 香子 Kyoko Yonezawa- Wieden+Kennedy Tokyo
Creative Tech Director
今回はAカテゴリー(デジタル・エクスペリエンス)を担当させていただきました。昨年はグランプリが出なかったこのカテゴリーですが、今年はデジタルプラットフォームの使い方もとても工夫されているものが多く、更には新しいプラットフォームを創りあげる意欲的な作品もみられました。他カテゴリーも含めたグランプリ選考会では本当にいろいろな声があがりましたが、ヒトの生活に密接に寄り添うもの、ヒトの行動を変える力のあるもの、が選ばれました。そしてどの枠にもあてはまらない、けどどうしても褒めたい「緊急開催!チンアナゴ顔見せ祭り! 」が特別賞に。審査委員が、審査委員の家族が、どんなにその企画が好きかを熱弁するとてもあったかい審査会でした。
 レイ・イナモト Rei Inamoto
レイ・イナモト Rei Inamoto- I & CO
Founding Partner
コロナの様な状況に世界が陥ると、世の中にとって何が本当に不可欠なのかが試される。
そして人が何を求めているかも、浮き彫りになってくる。広告が必要不可欠かと問いかけると、正直そうは言えない。
そんな中、ブランドとして、ビジネスとして生き延びるに必要なのは、経験や学習に基づいた知識ではない。
「想像力は知識より重要である。知識には限界がある。想像力は世界を包み込む。」
アインシュタインの言葉を思い出す。この逆境を乗り越え、新しい未来を描く想像力、そしてその未来を作り上げる創造力。即ち「クリエイティビティ」が何よりも大切になってくる。
ブランデッド・コミュニケーション部門の審査で今後の可能性を感じたのは、広告の枠を越え新しい可能性を見せてくれたアイディアを見つけられた事だろう。 - 電通
-
デザイン部門
審査委員長 永井 一史 Kazufumi Nagai
永井 一史 Kazufumi Nagai- HAKUHODO DESIGN
代表取締役社長
広告コミュニケーションより広い概念であるデザインが、どう既存の枠組みを広げていくことができるかという我々のミッションだと考えた。ディスカッションを重ね「未来に向けての可能性」を審査のクライテリアにした。グランプリは”分身ロボットカフェ DAWN ver.β”。障害を持った方と社会をつなぐためのデザインであり、1次審査の時から頭一つ抜けていた。企業のリソースを社会に問いを投げるためのアクティビティに昇華した”雑誌「広告」”。自分の住む街に対してのまなざしを生み出すための仕掛け”おさんぽBINGO”。CPRの普及活動である”CPR TRAINING BOTTLE” 。新しい価値観をカタチにした「BAUM」などが上位入賞した。デザインそのものに目を奪われがちだが、背後にあるのは、インクルーシブやロボティクス、地域とのエンゲージ、企業のCSV、サーキュラーエコノミーなど極めて今日的なテーマであり、未来に繋がる問いかけそのものだったように思う。第1回目は、いいスタートを切れた。来年にはデザインの持つ裾野の広さを活かせるよう、さらに多くのエントリーがあることを期待したい。
デザイン部門
審査委員 アストリッド クライン
アストリッド クライン
Astrid Klein- クライン ダイサム アーキテクツ
建築家
ACC TOKYO CREATIVITY AWARDSのデザイン部門の審査を通じて、とても刺激的な経験をさせていただきました。審査委員が多いとコンセンサスまでのプロセスが複雑になりがちですが、幅広いクリエイティブな分野に精通した審査委員が集結したことで、より多くの消費者の声をとらえた結果になったように思います。
広告は、興味や関心が薄かったり、または、ある意味洗練された消費者を、一瞬で驚きに包み込むようなインパクトを与えなければなりません。
今回は特に、スマートに社会の意識改革をもたらした「分身ロボットカフェ」や「CPR TRAINING BOTTLE」、また、プロジェクションマッピングのように、新しいテクノロジーで視覚的にまばゆい魔法を放った「MORI BUILDING URBAN LAB」や「SHISEIDO GLOBAL FLAGSHIP STORE」、さらに、シンプルながらも爽やかで楽しく、記憶に残る効果をもたらした「シャンシャンが家にくる日。」といった優れた作品を生み出した受賞者の皆様に心からの賞賛を送りたいと思います。 上西 祐理 Yuri Uenishi
上西 祐理 Yuri Uenishi- 電通
アートディレクター/グラフィックデザイナー
 川村 真司 Masashi Kawamura
川村 真司 Masashi Kawamura- Whatever Chief Creative Officer/Co-Founder
- WTFC Chief Creative Officer
デザイン部門は今回新設されたカテゴリーなので、作品自体に関する議論はもちろんのこと、この部門自体の存在理由や、どういった視点でどのようなポイントを評価すべきかといった広い議論ができ、審査をする側にとっても大変刺激的でした。
個人的には、デザイン部門は「広告」という枠に囚われず、もっと幅広いジャンル、例えばプロダクトやサービスやはたまたワークショップのような形のない仕組みといった有形無形あらゆるものを対象に、表面的なクラフトだけではなく社会的インパクトなども考慮しながら優れたデザインを選出すべきだと考えながら審査に携わりました。そんなジャンルレスな応募作に匹敵するほど多彩な審査委員たちのおかげで、この指標を体現するような素晴らしい作品を選び出すことができたように感じています。 小杉 幸一 Koichi Kosugi
小杉 幸一 Koichi Kosugi- onehappy
クリエイティブディレクター/アートディレクター
未来に向けて、
「デザインの可能性」をどう言語化するか。
そこに大きなテーマがあった審査だったと思います。
永井審査委員長の元、さまざまな「デザイン力」を持った審査委員との議論は、今までのACCの枠が外れた感覚、まさに審査自体が「可能性」に満ちたものだったと思います。
人によって「デザイン」の意味の重心が異なってくる時代。議論でもありましたが、「デザインの可能性」にピントを合わせた以上、部門名すら変えるくらいの言語化が、新しい価値に重点を置くこの部門には必要だと感じました。そう言った意味でもまだまだ可能性がある部門なんだと思います。
関係者のみなさま、
誘っていただいた永井さんありがとうございました。
そして受賞者のみなさま、心からおめでとうございます。 齋藤 精一 Seiichi Saito
齋藤 精一 Seiichi Saito- ライゾマティクス・アーキテクチャー
主宰
広告・デザイン・クリエイティブ。同じ業界に見えて、実は大きな壁が存在していたと思います。そんな壁を乗り越えて、それぞれの今までの立ち位置を維持した状態で分野を横断して良いものを見つけることの重要性を今回の審査から感じました。世の中を動かすこと、どちらの方向に動くべきなのかを指し示すこと、新設されたデザイン部門の受賞ラインナップを見ることそれが垣間見えると思います。短命なクリエイティブではなく、社会を俯瞰して考え創作物の実装維持をできる限り行い、業界の当たり前を疑うことのデザインがこれからも沢山出てくることを期待します。
 諏訪 綾子 Ayako Suwa
諏訪 綾子 Ayako Suwa- food creation
アーティスト
問いをデザインする。この正解のない時代に、予測の難しい今に、ひとつの答えを提示したり誘導するより、いかに美しい問いを投げかけるか。そういったエントリーに、デザインの新たな領域としての可能性を感じました。デザインとはなにか、そんな問いさえも、鮮やかに塗り替えて飛び越えていく、ますますこれからのデザインが楽しみです。
 太刀川 英輔 Eisuke Tachikawa
太刀川 英輔 Eisuke Tachikawa- NOSIGNER
主宰/ディレクター
広告デザインの終わり。プロジェクトの始まり。
ACCデザイン部門、初めての審査会。そこには企画・CM・インタラクティブ・グラフィック・パッケージ・空間など、あらゆるジャンルのデザインが応募されていた。
ただ不思議にも、審査委員全体には共通のクライテリアがあった。それらは世界と新しい関係を結び、同時にクラフトとして美しいデザインだ。
一体なにが共通しているのか。審査会の最後に、皆さんに問うてみた。今回選んだものは広告デザインではなく、世界に仮説を投げかけた「プロジェクト」のデザインかもしれない。そうだね、という共感が審査委員に広がった。
もうすぐ旧来の広告デザインは終わる。そして広告はプロジェクトになる。 中村 勇吾 Yugo Nakamura
中村 勇吾 Yugo Nakamura- tha
ウェブデザイナー/インターフェースデザイナー/映像ディレクター
審査会で再三行われた「なにをもって良いデザインとするか」という物差しに関する議論が個人的に興味深かったです。今現在私たちが包囲されている「希望」や「ビジョン」「善さ」などについて改めて考え直す良い機会でした。
 野崎 亙 Wataru Nozaki
野崎 亙 Wataru Nozaki- スマイルズ
クリエイティブ本部/CCO(チーフクリエイティブオフィサー)/取締役
クリエイティブの受け手である生活者が強制的な心理・行動変容を求められていた最中に、クリエイティブとしてどう向き合うことができるのかという点に注目していました。テクニックや然もありなんというような文脈よりも、出し手の“熱量や心積もりのある企て”を高く評価しました。また非常に素直でまっすぐなクリエイティブにかえって心を救われるという気持ちにさせられるものもありました。評価された作品たちはそのいずれも、作者の意図を超えて受け取る側の解釈の余地や前向きな勘繰りが生じていたように思います。作品が生活者側に取り込まれてナラティブな状況を生み出すこと、そんなクリエイティブに可能性を感じずにはいられません。
 ムラカミ カイエ Kaie Murakami
ムラカミ カイエ Kaie Murakami- SIMONE
CREATIVE DIRECTOR
社会需要の変化で、ますます深遠になる「デザイン」という言葉を冠した新設部門。初の審査会が、鋭く活発な議論の場になったのは言うまでもありませんが、結果、選出された受賞作品群から、今後この部門が果たすべき道筋が、朧げにでもイメージできたのは、大きな一歩だったと感じています。私はデザインという活動が、より良い世界を目指して変革を促すために、更に重要な役割を担っていくと信じています。来年、更なる応募やこの部門の発展によって、クリエイティブに関わる多くの人が、社会の改善や発展のために活躍の場を拡げていくことを、心から期待しています。
 八木 義博 Yoshihiro Yagi
八木 義博 Yoshihiro Yagi- 電通 CDC
クリエーティブディレクター/アートディレクター
デザインは、広告より大きな概念。既存の広告の枠を超えて、デザインが持つ可能性を垣間見れたことが今回の収穫でした。しかし、新しいデザイン部門として広告ではないプロジェクトなどが選びやすかった側面もあるかもしれません。落選の中にも、従来の広告のように見えて、そこから抜きん出ようとするもの、小さいながらも深くブランドが伝わってくるもの、評価に値する仕事があったように思います。広範囲のクリエイティビティを司るACCのデザイン部門からすれば、仕事の種類、大小に関わらず、ブランドにデザインをツールとしてどう使ったかを見極めることが必要です。異種格闘技戦にならざるを得ない審査の難しさを課題に感じました。
 山本 尚美 Naomi Yamamoto
山本 尚美 Naomi Yamamoto- 資生堂
チーフクリエイティブオフィサー
他のデザインアワードとは一線を画し、新しい意味としての「デザイン」にスポットをあて、これからの時代、「未来」のデザイン見据える深い洞察と刺激のある審査だった。エントリー作品にはビフォーコロナ、ウィズコロナの両時期に発信されたものが混在し、世の中が一瞬にして様変わりしていく局面を垣間見られた。作り手の熱量やユーザーの生活価値観、クライアントの意識の変化など審査委員にもそのセンティメントが伝わった。作り手の熱い思いに心打たれるものが多く、ひとつひとつの作品が終着点ではなく、「ここから始まる」という幕開けの期待感を与えてくれ、社会課題の解決にとどまらない、「その先」が映し出された仕事に心動かされた。
- HAKUHODO DESIGN
-
メディアクリエイティブ部門 審査委員長
 箭内 道彦 Michihiko Yanai
箭内 道彦 Michihiko Yanai- クリエイティブディレクター
- 東京藝術大学学長特命・美術学部デザイン科教授
メディアが前例と自尊に捉われず鮮やかに現在の社会と自身に対して機能するアイデアに出逢うべく、様々な発信の最前線から招聘した審査委員の面々。その男女比を1:3にしたのもメディアクリエイティブ部門からの一石。多様な議論が溢れる審査会でした。「こんな年こそ、新しいものを讃えたい」と言った審査委員の一言から一気にグランプリに駆け昇った考察と解読『感電』MV YouTube公開企画〔 STRAY SHEEP CODE 〕。感じたのは、米津玄師というひとりの人間の匂いです。これからのクリエイティブがどこへ向かうのかはわからない。いつの時代も、その時代に人間の身体と心が反応して、きっとクリエイティブは生まれていくのだと思う。AIにできないこと、そして委ねるべきことは確実にある。メディアは、感情の一番近くにあります。
メディアクリエイティブ部門 審査委員
 有元 沙矢香 Sayaka Arimoto
有元 沙矢香 Sayaka Arimoto- 電通
コピーライター/プランナー
もっと話したかった、というの正直な気持ちです。「メディアクリエイティブ」という部門は、これをメディアにしたか!というものから、メディアをこう使ったか!というものまで本当に多種多様。そして審査委員も多様。ひとりの意見で、みんなの意識が変わる。だから議論が面白かった。もっともっと話して、みんなでこれだ!とグランプリを決める達成感が欲しかったな・・・。でも、個人的にはグランプリになった「STRAY SHEEP」が好きでした。新しい場をメディアにするだけでなく、気持ちを動かし、人を動かし、クリエイティブの力も機能していた。これがグランプリなら、きっと来年もこの部門に自分も応募するなと思って投票しました。
 石井 うさぎ Usagi Ishii
石井 うさぎ Usagi Ishii- Google
Executive Creative Director
広告コミュニケーションの基本は「メディア X クリエイティブ」にあると言えます。メディアを広義の意味で捉えると、このどちらが欠けていても成立しません。今回はその「メディア X クリエイティブ」におけるビッグアイデアを審査する部門。多様な手口が繰り広げらる「アイデア群雄割拠」な様を目の当たりにしました。審査委員の皆さんと、お〜、王道まっしぐら!あっ、こんなやり方もありましたか!とコメントを交わしながら、個性あふれるエントリーを(画面の)前に、アイデアの新しさと技の高さに新鮮な没入感を覚えました。ワクワク、ドキドキ、グッとくる。どんな環境下でも人を動かす、そんなアイデアの強さに向き合えた審査でした。
 内田 佳奈 Kana Uchida
内田 佳奈 Kana Uchida- ライオン ビジネス開発センター
エクスペリエンスデザイン/マネージャー
今回初めて「メディアクリエイティブ部門」の審査に関わらせていただき、誠に光栄でございました。審査会では、様々なポジションの方々とともに「メディアの価値」に焦点を置いた多様性あるディスカッションが展開され、私自身とても学びの多い時間でした。広告として成り立つための「一定の成果」と、メディアが進化する可能性を秘めた「偉大なる一歩」を踏み出しているか。その両方を天秤にかけつつ企画が成り立っているかを検討し、審査に臨ませていただきました。また、応募作品はどれも「情報の受け手を如何に笑顔にできるか」という視点で工夫に富み、きちんと人間らしいコミュニケーションが形作られていたことが嬉しかったです。
 岡 慎太郎 Shintaro Oka
岡 慎太郎 Shintaro Oka- NTTドコモ
広報部 広報担当部長
昨年に引き続き、多才な審査委員の皆さんと審査会にて議論できたことは本当に幸運でした。
コロナの影響は確かにある。そんな時だからこそ元気や勇気や、ほっこりした気持にさせてくれるクリエイティブ。コロナを逆手に取った新しいクリエイティブ。コロナがあろうがなかろうが良いものは良いという本質を問いかけてくるクリエイティブ。たくさんの素晴らしいクリエイティブとの出会いがありました。何をもってメディアととらえるのか?昨年は悩んだこの問いも、悩むこと自体がナンセンスと思うほどメディアの概念は拡大しています。来年の成長が今から楽しみな「メディアクリエイティブ部門」に栄光あれ。 鯉渕 友康 Tomoyasu Koibuchi
鯉渕 友康 Tomoyasu Koibuchi- 日本テレビ放送網
人事局人事部長 兼 キャリアサポート部長
審査委員2年目ということもあり「メディアのアセットを活用した新しいアイディア」という審査基準への個人的理解も幾分進んだ上で、審査に臨むことが出来ました。未曾有の国難の渦中ということもあり、心の平穏を保ち、団結を呼びかけ、希望を見出そうとするクリエイティブが多かったように思いますが、感情に流されそうになるところ、コロナ禍のクリエイティブを審査するのではないと言い聞かせました。審査においては各委員の推し作品への「熱量」は意外と大きな要素なのですが、オンラインであっても十分伝わるそれぞれのプレゼンで、心配も杞憂に終わりました。グランプリ作品も審査委員の総意として、納得感のある結果になったと思います。
 坂井 佳奈子 Kanako Sakai
坂井 佳奈子 Kanako Sakai- ハースト婦人画報社
エル グループ 編集局長/エル デジタル 編集長
昨年に続き審査をさせていただきました。今年はコロナ過により広告のアプローチが激変した年となりました。そんな状況下での審査会はもちろんリモート。初の試みでしたが、箭内審査委員長のまるで大学講義を受けているようなスムーズな進行のもと、議論を深めることができました。シンプルに強いメッセーを届けるもの、デジタルやSNS、CMを駆使したダイナミックな広告、今年もクリエイティブな作品が揃っていましたが、やっぱり人々の心に届く作品には普遍的な強さを感じました。時代を超えて素晴らしいもの、広告を見るとその時代を感じるもの、今という時代のメディアの役割をきちんと果たしている、そんな素晴らしい作品が選ばれたと思います。
 佐久間 宣行 Nobuyuki Sakuma
佐久間 宣行 Nobuyuki Sakuma- テレビ東京
プロデューサー
メディアクリエイティブ部門の審査に参加させていただくのは2年目です。昨年の第一回から皆で悩みながらもともに価値観を作ってきた賞という感じがしてとても思い入れがあります。この大変な時代に表現や仕掛けをしていくこと、それがより多様で新しいこと、その志がある作品群を見ていくのは、とても勇気の湧くことでした。むしろ、「自分はどうなんだ?」と問い直されてるような気もしました。受賞した作品群を見ると本当にカオス!でもそれが、今この部門が最前線を担っていることの証明でもあると思います。参加できてよかったです。
 田中 美奈子 Minako Tanaka
田中 美奈子 Minako Tanaka- 博報堂DYメディアパートナーズ
クリエイティブディレクター/メディア・コミュニケーションプロデューサー
「メディアクリエイティブとは?」
その問いに、今の私なりの答えを出したいと思っていました。
メディアクリエイティブとは。
メディア、コンテンツ、クライアント、生活者、社会。
それぞれのルールや事情や当たり前。
その多様性をごった煮にして、ゲームチェンジを仕掛けていくこと。
2020年、みんなが等しく変化を迫られた世界。
だからこそ、手放せる当たり前は手放し、ファンや視聴者、共創するメディアやブランド、大切なものをちゃんと大切だと手に取り、新しい幸せの“型”をつくるゲームチェンジを目指したお仕事に、尊敬と、ワクワクと、嫉妬。
これからもみなさんと一緒に頑張らなきゃとパワーを頂きました。
多様な審査委員の方々とご一緒できたMC部門。
ACCの中でも、オンリーワンの色を生み続けられる部門だと感じ光栄です。
ありがとうございました! 中谷 弥生 Yayoi Nakatani
中谷 弥生 Yayoi Nakatani- TBSテレビ
DXビジネス局長
2回目の審査をさせて頂き、コロナの状況下で制約があった中でもエントリー作品が益々パワーアップされており、本当に勉強になりました。
審査会でも発言しましたが、グランプリを取った「STRAY SHEEP:CODE」や、「バーガーキング下北沢店」、「サントリー×ドラゴンクエストウオーク自動販売機」等、ユーザーが仕掛けに反応・行動して初めて完成し、大きな宣伝になるような取り組みを面白く拝見しました。どうしてもテレビは一方通行になりがちなので、反省するとともに、色々、考えさせられる審査会でした。貴重な機会を頂きありがとうございました。 秀島 史香 Fumika Hideshima
秀島 史香 Fumika Hideshima- FM BIRD
ラジオDJ/ナレーター
ハッとするような鮮烈な視点、「やられたなあ」とニンマリしてしまうアイディアの数々に、頭の中を気持ち良くシャッフルされ、アップデートされた気分です。異なるジャンルを横断する皆さんとオンラインで集まった現場は、それぞれの背景と価値観、視点も角度も入り乱れるジャンクションのよう。「同じ作品でも評価がここまで真逆なのか!」と純粋に驚いたり、ハッとする発見がありました。不安なニュースが目に耳に流れ込んでくる時代だからこそ、メディアは何ができるのか。誰のため、何のために発信するのか。人の心に残り続け、日々の暮らしを少しでも良く変えていくエネルギーこそ本質であると、今まで以上に強く意識した年でした。
 平池 綾子 Ayako Hiraike
平池 綾子 Ayako Hiraike- 資生堂ジャパン
メディア戦略部 メディアバイインググループ
グループマネージャー
最終審査で他の委員の意見を聞いて、個人での一次審査の時から作品への評価が変わることがあります。それは、自分の軸に新しい見方が加わって、アイデアへの認識が一歩進むと感じられるから。これこそ「広告」の楽しさだと思います。
今回、私が魅力を感じた作品に共通していたことは、広告メッセージの投げかけに呼応して、心が動かされ行動が促されるという“Call & Response”が、地域、ファンベース、会社といったコミュニティーで行われている点です。マスメディアを使っていてもターゲットは絞られていて、広告が「プライベート化」していく時代の流れを垣間見ました。改めて「広告」ってなんだろう?と立ち止まって考えているところです。 横山 祐果 Yuka Yokoyama
横山 祐果 Yuka Yokoyama- AbemaTV
プロデューサー
サイバーエージェントとして初めて審査に参加させて頂きました。100点を超えるエントリー作品に刺激を頂いたばかりでなく、審査委員の皆様の様々な角度からのご意見を伺えるという贅沢な時間を過ごさせて頂きましたこと、心より感謝申し上げます。
新しい日常を迎えている今だからこそ、人との温かい繋がりを感じながら伝播していくような、そして何よりも明るいパワーをもらえる作品であるということを軸に選出させて頂きました。メディアとアイデアのハッとさせられるような掛け算に触れる度、ワクワクが止まりませんでした。
メディアの価値を最大限に活かした数々のアイデアから得た学びを胸に今後も精進して参りたいと思います。 -
クリエイティブイノベーション部門
審査委員長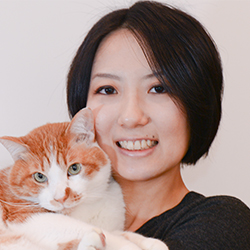 米澤 香子 Kyoko Yonezawa
米澤 香子 Kyoko Yonezawa- Wieden+Kennedy Tokyo
Creative Tech Director
イノベーションとは一朝一夕で為るものではなく、長い時間のあと振り返ったときに、あ、あれが転換点だったな気づく、そういうものではないでしょうか。なので、「テクノロジー×ビッグアイデア」がテーマの部門ではありますが、それに並ぶほど大切なのは「社会に根付くか・未来を創れるようなポテンシャルを有しているか」という視点です。社会に根付かせるためには、作品そのものの力に加えて、造り手および使い手の意志の力がとても重要になってきます。今回は、そういった意志をもつ作品に多くエントリーしていただいたと感じました。
グランプリを受賞した「分身ロボットカフェ DAWN ver.β」は、その意志をものとても強く感じた作品です。エントリー自体はカフェというタイトルになっていますが、プレゼンを通してカフェという場だけでなく、そこにたどり着くまでのロボット・オリヒメの開発、オリヒメをいろんな方が操作できるUIの開発、カフェをきっかけにさまざまな企業や県庁での就職につながったお話、そして今後も世の中に定着させていくんだという強い意志を伺うことができました。
贈賞式の場面では、使い手であるマサさんに「オリヒメと出会ったことで人生が良い方向に変わりました」と仰っていただき、この作品をグランプリに選ぶことができて本当に良かったと改めて思いました。今後のご活躍も、楽しみにしております。クリエイティブイノベーション部門 審査委員
 岩下 恵 Kei Iwashita
岩下 恵 Kei Iwashita- IDEO Tokyo
Design Director
今年も多くの素晴らしい作品が集まり、たくさんのインスピレーションをいただきました。
審査には非常に悩まされましたが、高い評価となったのは「劇団ノーミーツ」のようにコロナ禍でのピンチを逆にチャンスと捉え、長年変化が見られなかった業界を前進させる、革新的な体験を提案した作品ではないかと思います。
また、個人的にはテクノロジーをあくまでも手段・補佐として位置づけ、使い手の世界を広げることにフォーカスした作品が好印象でした。「分身ロボットカフェ」、「ゆらぎかべ:TOU」、「UNLABELED」はどれも高度な技術を要する一方で、人の創造性を豊かにしたり、構造的なバイアスから逃れて自分らしく生活することを可能にしてくれる作品です。製作者の創りたい未来に対する、たくさんの共感が集まった会だったと感じております。 小野 直紀 Naoki Ono
小野 直紀 Naoki Ono- 博報堂
『広告』編集長/monom代表
「イノベーション」という言葉がバズワードになって久しいが、あらためてイノベーションの定義を考えるいい機会になった。応募作品については、今回入賞したようなレベルの高いものから、ほかの部門のついでに応募してきたようなものまで凸凹があった。そのため、花火的で継続性の感じられないものもまま見受けられた。たしかに花火は社会を変えるきっかけをつくる重要な手段である。しかし、きっかけだけで終わらず、社会変革に関与し続ける姿勢と成果を評価したいと考え審査にあたった。それが、発明と革新の間にある大きな溝だと考えるからだ。結果的に、革新に向き合う熱量が感じられるものが受賞を勝ち取っていったように思う。
 木下 真吾 Shingo Kinoshita
木下 真吾 Shingo Kinoshita- NTT 研究所/主席研究員・研究部長
- 大阪芸術大学 アートサイエンス学科/客員教授
- 電通 Dentsu Lab Tokyo/客員主席研究員
コロナで全てが変わってしまったこの一年、応募内容にもその影響が大きく出ることが予想されたが、入賞作品としてはわずか「劇団ノーミーツ」1件のみとなった。本部門が、アイデアや表現だけではなく社会への実装を念頭においた時間の要する取り組みを対象とすることを考えれば、来年はウィズコロナに資する応募が増え、実際に社会の変革ドライバとなっていることを期待したい。今回グランプリを受賞した「分身ロボットカフェ DAWN ver. β」は、もともとコロナ禍を対象としたものではなかった。しかし、リモートワークが当たり前となった今、多くの人々に対して、障がい者の方などに与えた本取り組みの価値を自分事としてとらえるいい機会となった。その意味では、まさにコロナ禍だからこそ普遍的な価値として高く評価された取り組みともいえる。来年の今を想像することは難しいが、クリエイティブな取り組みによって、来年の今を創造することはできると信じている。
 キリーロバ ナージャ
キリーロバ ナージャ
Nadya Kirillova- 電通
クリエーティブ・ディレクター
クリエーティブにおけるイノベーションとは何か。ここ数年、とても考えさせられるテーマだ。広告賞だと「イノベーション」がつく部門は、新しいテクノロジーを使ったり、ソーシャル課題の解決に取り組んでいるものが多いが、本当にそれだけでいいのだろうか。選ばれるものは、この業界が作ったルールに引っ張られていないだろうか。本質的に社会を動かしているだろうか。クリエーティブなイノベーションは、この部門ができるずっと昔から自由自在なカタチであらゆるところで生まれている。だったら、もっと多様な切り口やコミュニティーから飛び出してくる広義の意味でのクリエーティブイノベーションを発掘し、選ぶことが必要なのかもしれない。
 徳井 直生 Nao Tokui
徳井 直生 Nao Tokui- 慶應義塾大学/准教授
- Qosmo/代表取締役
- Dentsu Craft Tokyo/Head of Technology
コロナ禍の2020年。否応なく受け入れざるをえなかった新しい生活様式が、社会の問題点をあぶり出し、各々の価値観を見直す良い機会になったことは間違いないでしょう。実際に今回の応募作品の多くからは、これまで当たり前としてきた「常識」を疑う目線が強く感じられました。寝たきりの人は働けない、人が集まらなければ演劇はできない、知財とは小難しいものだ... そうした常識に、テクノロジーと創造性、そして時にユーモアを手に挑む多くの方々の姿に、感銘を受けました。次の時代の常識は、皆さんの非常識から生まれます。新しい非常識を広めるお手伝いをする。この賞の意義を改めて実感した審査会でした。
 中西 裕子 Yuko Nakanishi
中西 裕子 Yuko Nakanishi- 資生堂 R&I戦略部
資生堂オープンイノベーションプログラムfibonaプロジェクトリーダー
COVID-19により社会や人の価値観が大きく変化する中での審査は、自分にとっての「こうあってほしい未来」を、応募された作品を通して再度考え、言語化する良い機会で、さらにはそれを、様々なバックグラウンドを持つ審査委員の方々と議論できたことはとてもエキサイティングな体験でした。最終審査では、テクノロジーというそれだけだと一見無機質なものを用い、人間にとって有機的で意味あるものに変化させる作り手のクリエイティビティ、さらにはそれをビジネスにスケールアップさせるための情熱に心を動かされました。日本や世界を変えていくイノベーションの本質的な思想に触れられて、大変幸せな時間でした。
 中村 洋基 Hiroki Nakamura
中村 洋基 Hiroki Nakamura- PARTY/Creative Director, Founder
- ヤフー/MS統括本部 ECD
まず、お招きしてくれた米澤さん、ありがとうございます。
私は10年前「アワードとってブイブイ言わすゾ!」とイキってた若者でしたが、今は「マーケティング戦略上、いかに並外れた数値を出すか」「イノベーティブは広告以外の事業でやろう」と舵切りして、広告賞にとんと疎くなっていました。
審査は、スレてない方たちが、フェアに「革新的?」「社会に影響を与えそう?」そして「何が好き?」についてアツく議論する、最高に気持ちのいい場でした。
この部門、もっと応募が増えればいいなあ。応募増えると受賞作品も増えますよ。「あれ?これ応募していいの?」とたららを踏んだサービス・プロトタイプ。それグランプリかも。来年ぜひ! 福原 志保 Shiho Fukuhara
福原 志保 Shiho Fukuhara- グーグル/テクノロジーインテグレーションリード
- bcl
- HUMAN AWESOME ERROR
イノベーションというものは、規模に関係なく日常がらっと変わってしまう技術や仕組みの種であり、ポピュラリティを獲得していることは関係なく、また、期間限定のキャンペーンのように1、2年経ったら忘れてしまうような強度のものではありません。何かを変えたい、そういう強い意志を感じたいのです。
今回の審査は「イノベーション」として見れるものが少なく苦しかったです。応募動画でSNS等の拡散数を見たら萎えます。イノベーションなのですから、まだ名もなく認知されていないものでも応募してほしい。
生まれたばかりのこの部門がただの枠外扱いではなく、クリエイテビティとは何かを示唆する場になってほしいと願います。 坊垣 佳奈 Kana Bogaki
坊垣 佳奈 Kana Bogaki- マクアケ/共同創業者・取締役
広告賞におけるイノベーション部門で、何をどう評価するのが適切なのか、、、
広告の分野の知見があまりない私にとって、その問いにはっきりとした答えはないままの審査参加となりましたが、他審査委員の皆さんとの淀みない議論の中で、その問いへの答えを追求する気持ちはだんだんと消え、純粋に心に響き、かつ世の中にちゃんと届いて人の行動に変容を促すものはなんなのか、そこに向き合えていた自分がいました。
いつの世もきっと、人の心を大きく打つものしか、人の行動を変容させ、世の中を変化させることはできない。それができるのは、本気で世の中を変えたいと思う気持ちと、そこに向かう並々ならぬ努力と、それを支える仲間の存在なのだと思います。
素晴らしい上位作品の数々に、それを改めて教えていただきました。
ありがとうございました。 松島 倫明 Michiaki Matsushima
松島 倫明 Michiaki Matsushima- 『WIRED』日本版 編集長
テックはビッグアイデアの夢を見る──でも実際のところ、イノベーションとはいつだって、ささやかで斬新的なものであり続けた。であるならば、ACCクリエイティブイノベーション部門とは、果たして何を顕彰するのか? 例えば技術史家のメルヴィン・クランツバーグはかつて、「発明は必要の母」(その逆ではなく)と言っている。最高のアイデアは次のアイデアを誘発し、いまこそクリエイティヴが必要なのだと創造者たちを鼓舞する。今回の審査で選ばれた受賞作も、次なるイノベーションを準備するだろう。だから本当にこの賞が贈られる先は、未来そのものなのかもしれない。
 暦本 純一 Jun Rekimoto
暦本 純一 Jun Rekimoto- 東京大学/教授
- ソニーコンピュータサイエンス研究所/副所長
今年のACCクリエティブイノベーション部門は、米澤新委員長の元、新たな体制で審査に望みました。テクノロジーとしての新規性と、プロダクトとしての完成度はなかなか両立しがたいものですが、それぞれのエントリーのもつ良さや可能性をできるだけ引き出すことに留意して審査しました。今年は、特に新型コロナウィルスにより世界的に閉鎖的な雰囲気が蔓延する中、それを乗り越える可能性を提示してもらえるエントリーがあったことに、審査委員としても勇気づけられました。
- Wieden+Kennedy Tokyo





今年も才能に溢れ、輝かしい結果を残してきている現役のプレイヤーに集まってもらった。故に、それぞれの異なる価値観で自分に正直に審査してください、とだけ伝えさせてもらい審査を始めた。
Bカテゴリーについて。
昨年に引き続きメダリスト以上とそれ以下の間に大きな差があった。Web広告に対して世の中が以前ほど寛容ではなくなったことが原因なのだろうか、新しい突破口を模索している時期のように見えた。
その中でグランプリに推す意見が多かったのは、2連覇を狙うjmsの10秒ドラマ、加賀市、日清匂わせたい、の3作品。完成度としてはjmsだったが「匂わせたい」の持つ、今の空気を纏った新しい可能性にかける結果となった。いわゆるグランプリ感に欠けるように見えるかもしれないが、それこそがこのカテゴリーの最大の武器なのではないだろうか。考えすぎず、カジュアルに、鮮やかに。
Aカテゴリーについて。
トヨタイムズ、BOSS、カネボウ、Netflixの4作品が頭ひとつ抜けた。それでも依然として意見は別れ接戦であった。この4作品はどれも似ていない。そしてどれもがグランプリまであと一歩だった。さらに議論を重ねて最後は2作品の一騎打ちとなった。
カネボウは若い感性が放つ伸び伸びとした映像と音楽の力が圧倒的であった。商品や企業へのリンケージが弱いのでは?という意見もあったが、「わかりやすい病」にかかって袋小路を彷徨っている広告関係者に、受け取る側の解釈を信じること、「余白」の大切さを思い出させてくれた。
それに対してNetflixは、CM も含めた日本のエンタメ全体が陥っている「事なかれ主義」に対して、人が見たいのは綺麗事でなく、ドロっとした人間の本質なのだという企業の「哲学」を力強くゴロっと形にした骨太な作品。そこに漂う「不良性」も今や希少な香りだ。
「哲学」のネットフリックスか、それとも「余白」のカネボウか。
このチームでおこなわれた全ての議論と、それによって導き出された全ての結果を誇りに思う。広告の手段が多岐にわたり、今やオールドタイプと言われそうなフィルム部門ではあるが、長い歴史を経てもCMは依然として強く効果的な広告手法であり、様々な制約を受け限定された条件の中で鍛えられ生まれたアイディアたちは逞しい、と感じさせてもらった。伝統主義者と言われるのならば、それも仕方がない。チームのメンバー全員に深く感謝したい。
そして今、フィルム部門をちょっと愛しく思っている。